第14期科学ジャーナリスト塾を終える
会員提供の著書で、体験・証言を学ぶ
第9回「現場でしか見えない原発被災―福島で伝えること」
第8回「地球温暖化をどう伝えるか」
第7回「アポロの月着陸を米国に取材して学んだこと ―『地球環境問題の大切さ』と『品質管理技術の大切さ』」
第6回「新聞の投稿欄に書いてみよう」
第5回「聴きだす力、伝える心 ―塾生を取材する、塾生が発信するために― 」
第4回「南極観測隊に同行取材して学んだこと ―『国家とは何か』『科学の国際協力とは何か』」
第3回「『私が受けた作文教育』を読み合う」
第2回「歴史を記録する―科学ジャーナリストのもう一つの役割」
第1回 ガイダンス「塾で学んだこと、学ぶこと―体験を未来に」
科学ジャーナリスト塾の概要
2015年10月から始まった第14期科学ジャーナリスト塾は2016年3月9日、全日程を終えた。塾生は19人。期間中に計10回、水曜日夜の時間に、科学ジャーナリズムや科学コミュニケーションについて実践を交えて学んだ。最後まで熱心に通う塾生も多かった。
今期は「体験を未来に」を主題に、過去の報道の検証をしたり、福島の被災地での報道現場の声を聞いたりした。扱う話題は原発事故だけでなく、航空機事故、南極観測、宇宙開発、温暖化など多彩で、9人の講師のほか文章アドバーザー、サポーターなどの協力を得て、塾生には積極的に文章を書いてもらった。
実習例として「講師の話を記事にする」「新聞への投書記事を書く」「一つのモノを使って自己紹介する」などしたほか、講師の話の後に塾生同士がグループ討議することで、互いの関心事を知る機会も作った。毎回の提出文の一部は、このようにJASTJホームページの塾コーナーにアップしたのが今回の最大の特徴となった。
塾は、健全な科学ジャーナリズムの発展のために、会員のボランティア精神で進めている活動だが、今期の成果を生かして2006年度も秋から第15期の塾を開催したいと計画している。第14期の塾を終了するに当たって、塾生の感想・意見の一部を紹介しよう。
■
〔塾を終えて〕
理系だからこそ、伝えられる面白さ 平清水元宣(塾生)
私は、この塾に参加して本当に良かったと思います。
”科学”という分野は、突き詰めると非常に多くの分野を横断しています。単純に物理・化学・生物・地学というような捉え方だけではなく、政治・経済・倫理・経営なども背景に考えなければ、”科学”の今後の展望は読めません。塾には多様なバックグラウンドや職業に就いている塾生及び講師の方、アドバイザーの方々がいたおかげで、一つの事象に対して、自分一人では到底思いつきもしない発想や知ることのなかった知識を得ることができました。
また、塾のテーマの一つに「失敗から学ぶ」というスローガンがありました。塾の内容も比較的に過去の事例をみんなで検証する、という姿勢が強かったように思います。過去に起きた事件や出来事を記録し理解することは、科学記者の大切な役割です。過去の記事は科学技術史となり、科学の進歩の軌跡となります。科学の今を伝える人間にとっては、過去を知らないと今や未来の予測できません。改めて「失敗から学ぶ」ことの意義を感じることができました。
理系なのに「文章書けるの?」と世間一般ではよく思われるかもしれませんが、理系だからこそ書ける真実や、伝えられる面白さがあるのだと私は思っています。畑は違えど、志の近い方々にお会いできたことも、私にとっては大きな財産でした。
文章アドバイザーのスタッフの方々及び、ゲスト講師の先生方、誠にありがとうございました。
■
伝えたいのは「知る喜び」と分かった 大崩貴之(塾生)
科学を伝える手段はたくさんある。話す、見せる、そして書く。どれを武器として使うかという差はあれど、目指すところは同じである。どの手段で伝えるかはさておき、まずは科学を伝えている先人の話を聞いてみたい――。確たる理想もないまま、漠然と科学コミュニケーションに携わる職へのあこがれを抱き始めた私がこの塾を受講した理由は、陳腐なものだった。
出発点が低かったこともあり、講座に数回参加した時点ですでに大きな成果があった。それは、上記の考え方の間違いに気付けたことである。確かに科学を伝える手段はたくさんあるが、目指すところも同様にたくさんあるのである。書くという手段でいえば、知る権利に応える科学ジャーナリストと、好奇心を掻き立てるような話題を提供する科学ライターとでは、その目的が異なるというように。
この違いに気付けたことは、科学を書いて伝える作法を学べたことより、私にとってずっと価値あるものであった。「どのように」科学を伝えるかではなく、「何を」伝えたいのか、自分の目指すところが明確になったのだ。清く正しい知識ではなく、知らないことを知る喜びを、私は伝えたい。 こんなことは本来なら事前に気付いておくべきことで、受講してようやく立つべきスタート地点が見えたといったところだろうか。自分のやりたいことに気付かせてもらったことを塾に感謝しつつ、同時に判明したこれから学ぶべきことの多さに、ただ呆然としている。
■
科学ジャーナリズムの面白さと「べき」論の違和感 中道徹(塾生)
塾の最初に北村行孝講師から日航ジャンボ機の御巣鷹山事故の話を聞き、また2月の月例会報告でMRJ(三菱リージョナル旅客機)について書いたので、この塾の間、私は飛行機のことばかり考えることになった。
実は、現在改正が議論されている我が国の民法は19世紀にできたものなので、飛行機は民法よりも若い。こう考えると、科学技術のダイナミズムや法律の鈍重さが良く分かる。こんなダイナミックな分野の話がつまらないはずはない。最先端の専門用語を分かり易く解説してくれる科学ジャーナリズムが、多くの人の心を捉えるのはこの辺りであろう。
私も、北村講師や鈴木教授などの著書を数冊読み、飛行機について改めて知り、どうして自分が航空学を志さなかったのか悔むほどだった。それだけ、飛行機やその安全性を支える技術が魅力的に記載されていた。これが科学ジャーナリズムの面白い点だと、私は考える。塾生で議論しても、この辺は楽しかった。
他方、議論が「べきだ」論になるときは、若干平凡になってしまう気がした。「べきだ」論は、本来、社会科学や人文科学にも及ぶ話なので、その分野での議論の成果を踏まえないとならないはずである。なのに、塾生で議論しても、情に訴える展開となっているように感じられることが時々あった。しかし、素朴な感覚で地動説の説得ができないのと同じで、素朴な「べきだ」論では社会の説得は困難だろう。この点で、科学哲学や正義論と科学ジャーナリズムがどう係わるのかも知りたかった。
鈴木教授は、月例会で、落ちない飛行機を作るのが究極の目標だと話された。人工知能に及ぶその話しぶりから、単に人道上の要請ではないと感じた。むしろ「べきだ」論を捨象し、このように解そのものも科学技術で示す方が潔いと感じられた。
〔事務局注〕中道さんはJASTJの会員でもありますが、塾生の研鑽の機会として月例会の会報執筆を依頼した経緯があります。
第14期の塾では、当会議(日本科学技術ジャーナリスト会議、JASTJ)の会員が執筆した著書を、教材として大いに活用した。著者からは塾生に無料提供いただくなど、全面的な応援をいただいた。
歴史を記録することの意義を学ぶ11月4日の塾では、講師の北村行孝さんが自らの著書『日航機事故の謎は解けたか』(花伝社発行)を塾生にあらかじめ配布、読んできてもらっての講義だった。1月13日に武部俊一さんが文章の書き方を指導した際は、JASTJ編さんの『科学ジャーリストの手法 プロから学ぶ七つの仕事術』(化学同人)の中から武部さんの記事の「科学ジャーナリストの文章作法13箇条」を紹介しながら、塾生が書いた原稿に赤字を入れた。
クリスマスを前にした12月16日、牧野賢治さんから自らの体験を綴った『科学ジャーナリストの半世紀 自分史から見えてきたこと』(化学同人)が塾生にプレゼントされた。著者の半生とともに日本の科学ジャーナリズムの歩みがたどれる本だ。塾事務局からもJASTJが20周年を記念して発行した『科学を伝える 失敗に学ぶ科学ジャーナリズム』(JDC)を提供した。過去の塾で伝えた科学記者の失敗事例などを学んでもらうことが狙いだ。
ベテラン会員が著作を通じて塾への支援くださるのは有難い。88歳の大ベテラン科学記者の堤佳辰さんからは『原子力報道五十年 科学記者の証言』(エネルギーフォーラム新書)を「塾生に読んでもらって」と提供された。この一冊は、堤さんと同じ新聞社で記者を目指す塾生に読んでもらった。
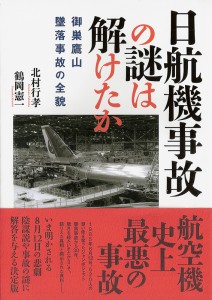




科学ジャーナリスト塾に提供された書籍
堤氏の『原発報道五十年』を読んで 遠藤智之(塾生・筑波大学大学院生命環境科学研究科)
『原子力報道五十年 科学記者の証言』を拝読した。著者の堤佳辰氏から、「ぜひ塾生に」とのことで塾長より私の手元へ。堤氏は1950年から日経記者として、科学技術の取材にあたってきた。メディアの道を歩もうとしている私にとって、まさに「大先輩」である。
本書では、日本が原子力の平和利用を志してから、現在に至るまでを書いている。日本の原子力開発は、米国が濃縮ウランの供与を決めたことを受け、政府主導で始まった。その後、学界や産業界が加わり、開発が進められ、日本経済を支える基幹エネルギーとなった。
福島原発事故は、堤氏の退職後に起きた。堤氏は「“想定外の高さ”の津波による浸水で全電源を喪失、緊急冷却システムが機能しなかったことが真因である」とした上で、「津波に耐える原発は既に存在する」という。自然循環で、高温炉心の冷却が続く受動安全炉だと紹介。現用の能動安全炉と比べ、電源喪失や人為ミスに強く、米国では審査中で正式認可が迫っているとのことだ。
堤氏は、「やめれば安全、なければ安心」という脱原発の思潮を、「資源もエネルギーもないない尽くし、少子高齢化の日本にとって“滅びの道”」「一国のエネルギー政策は単に国民や為政者の“好き嫌い”では決められない」と批判する。合理性、現実性、何より経済性が優先するべきだという。
日本政府によれば、2030年の電源構成として、再生エネで22~24%、原子力で20~22%、ほかを火力で賄うとしている。もし、この水準を維持するなら、原発の再稼動だけでなく、原発新設の議論も必要となる現実がある。過去の原子力政策の報道に当たった思いやその舞台裏を本音で伝えた大先輩の書に学ぶ点は多い。
本書を読み、理想で終わらず、現実的な未来への道筋を描く大切さを痛感した。これから記者として、私にもその責任がある。「道は歩いた跡にでき、未来は常に現在の延長線上にある」と堤氏。未来を示す役割を担う者として、過去の足跡を知れたことは、今後の糧となるだろう。(2016年3月提出)
2016年2月24日(水)の科学ジャーナリスト塾では、朝日新聞編集委員の上田俊英さんが「現場でしか見えない原発被災―福島で伝えること」というテーマで講演しました。塾生からの参加してみての記事が寄せられています。ご覧ください。
〔塾生の投稿記事から〕
原発報道と科学記者 〜3.11を教訓に〜 平清水元宣(塾生)
あの日、世界中の人々が被災地を心配していました。
東日本大震災から間もなく、五年が経とうとしています。今も被災地の復興は行われていますが、復興だけすればそれで良いのか。科学報道の在り方や考え方の課題を提起して頂いた第9回の講演となりました。
2月24日、朝日新聞報道局編集委員の上田俊英さんを講師に招き、「3.11の原発問題と報道」をテーマに塾が開かれました。当時の福島の様子の詳細な説明や、大地震がもたらした東京電力福島第一原子力発電所事故の悲惨さを生の声を通して教えてもらいました。
原発事故での放射能汚染による甲状腺ガンの増加を始め、復興の現状、帰宅困難者の数、発生時の避難情報の不十分さなど、多岐にわたる内容でした。充実した講演内容でしたが、それでも上田さんは言います。「福島の”今”を伝えるのは本当に難しい」と。私がお話を聞いて感じたのは、もしかしたら上田さんは一人の科学ジャーナリストとしての志と、新聞社という「組織ジャーナリズム」の重要性との間に強い葛藤も抱えているのではないか、というような印象も受けました。
また、復興現場では急激な人口減少が問題視されていることを知りました。全国的に人口減少が問題とされていますが、福島のそれは比ではありません。人口減少はそのまま人手不足へと直面し、雇用の減少は産業の衰退を意味します。議論の場では、労働力の仙台一極集中などの課題もあるという意見も出されましたが、故郷を離れざるをえない生産年齢人口の流出が問題点ではないか、と私は思います。
この塾のテーマの一つでもある「科学報道とは…?」については、上田さんは「現象を理解し、未来を予測すること」と述べていました。「科学が導くのは確率的な答えであり、明確な答えと確率的な答えは同じではない。微分は変化の割合を表し、積分は変化する未来を予測する。しかし、科学報道には数学的な論理的根拠も必須だが、哲学的な倫理観も必要で、「人の気持ちを含めた報道」を忘れてはいけない」とアドバイスを下さいました。
3月11日は毎年必ず来ます。たった五年の時間にもかかわらず、既に関係ないと思っている人が増えているように私は思います。被災した人が同じ国民に何人もいるという現実を忘れてはいないでしょうか。原子力発電所の要不要ばかりに振り回されてはいないでしょうか。
この経験は後世に語り継ぎ、日本だけでなく震災に直面するであろう世界中の国々で共通認識にすべきだと思います。震災の教訓を記録し、世界に発信することも、科学ジャーナリストの重要な役割なのだと再認識した第9回の塾でした。
話題提供してくださった上田俊英講師、誠にありがとうございました。




第9回塾のようす(撮影:都丸亜希子)
科学的な理解が先か、身近な関心が先か―塾生論議 佐藤年緒(塾長)
2月10日、毎日新聞の元論説委員で現在淑徳大学客員教授の横山裕道さんを講師に「地球温暖化問題をどう伝えるか」をテーマに塾を開きました。事前に発信したレジュメとパワポを使った講義ののちにグループディスカッションに移り、塾生5人を講師・サポーターら6人が囲んで参加するフルメンバーでの濃密な2時間でした。
温暖化がなぜ起きるのか、その科学的な論拠は何か。懐疑論の紹介を含め、温暖化メカニズムを科学的に理解することや証明することの難しさも改めて学びました。そもそもなぜ、二酸化炭素は温室効果の大きいガスでありながら、大気中の窒素分子がそうでないかを科学的に分かりやすく説明するのは意外に難しいとのことでした。
温暖化を伝えるうえで、メカニズムを理解することがまず大事か、それとも身近に起きていると気づく異変や関心事から入る方が分かりやすいのか。そもそも温暖化がなぜ悪いのか、といった根本的な疑問も含めて、5人が率直な意見を出し合っていたことが印象に残りました。
人類が近代文明を築きあげる以前から、地球史の中で氷期と温暖な時期を繰り返していた事実と、いま言われている温暖化傾向をどう区別するのか、その点を横山講師はさまざまに説明していました。教科書的な知識としてではなく、塾生にとっても意外に難しい「私にとっての温暖化問題」。その日、出席できなかった塾生にとっても、一緒に考える価値のあるテーマでしょう。
写真(サポーター都丸さん撮影)はグループディスカッションの風景。サポーターの柏野さんが提供してくれた広島県尾道産の粒の大きなミカンを口に含みながらの論議でした。温暖な瀬戸内海沿岸で獲れるこのようなミカンも、さらに1-2度温暖化が進めばどうなるかな、とふと考えます。栽培樹種は変わらなくても、雨が多くなり、害虫が増え、菌の繁殖が活発になり…と。
ますます日常と関係する温暖化について、科学を伝える者として関心を持ち続けてほしいと思います。話題提供をしてくだった横山講師、ありがとうございました。


第8回の塾のもよう(撮影:都丸亜希子)
■
第8回「地球温暖化をどう伝えるか」の塾を見守って
問題の枠組みを明快にしよう 読者に「響く」記事を書くために 荒川文生(サポーター)
20年来、環境問題と取り組んでこられた横山裕道講師のお話の重みは、ずしりとしたものを胸の中に残すものでした。地球環境問題が、これ程までに複雑で、人々の理解が得にくいものであることをいまさらのように感じつつ、それゆえに、この問題をどう伝えるかを塾生と共に考えようという講師の控え目なお姿に、尊敬の念を新たにしました。
複雑な事象の報道に反省
講演内容の概要はレジュメに譲りますが、もっとも重要なことは、補足資料として配られた毎日新聞の2つの社説(2001年10月28日と2003年1月6日)の違いを通じて、ご自身の問題の理解が当初、いかに浅いものであったかの反省を含めてお話を進められたことです。つまり、問題となる事象は複雑であり、問題を受け止める人々の状況が多様であるなかで、当初、懐疑論(楽観論)に影響される面があったけれども、問題を追及すればするほど、人間も自然も「急激な」変化には耐えられず、生物が大量に絶滅するという地球史を観れば明らかな事実に基づき、読者に「響く」記事を書かねばならぬと痛感していることが強調されました。
そこで「響く」とはどういうことかを、塾生と共に考えるというのが講演の後半の主題となりました。講師から次々と発せられる質問に答えるうちに、塾生の考え方も深まっていったように思われます。その中でも、要点のひとつとなったのは、「読者は何を考えているか」を意識することが「響き」を呼ぶということでしょう。
受け止める人の状況はさまざま
「響き」を呼ぶということに対する塾生の反応はさまざまでした。「問題となる事象の構造を解説するよりは、読者の背景を把握して、その関心に応えることだ」「いや、その両者のバランス、つまり、重点の置き方が大切だ」「結局、哲学・倫理に精通した専門家に整理を委ねよう」「人々の関心の度合いに応じて開発予算が決まるように、記事の書き方も人々の関心の度合いに応じて決まるものだ」「科学ジャーナリストは、専門家の考えを伝えるより、自分の考えをドライに伝えるべきだ」などなど…。
新聞読者の一人として環境問題の報道ぶりを論評するならば、その記事が何を問題としているのかという問題の枠組みを曖昧にしているものが少なくないと懸念しております。問題は政治課題なのか、経済対策なのか、あるいは自然と人間の存在に係るものなのかなど、その枠組みを曖昧にしつつ、読者をある方向に誘導しようとするような記事は、その信頼度を著しく低下させます。その意味で事象が複雑で、受け止める人々の状況が多様である問題を報道するに当たっては、問題の枠組みを明快にすることで記事の信頼度を高めれば、読者に「響く」記事が書けるのではないでしょうか。(了)


講師と塾生間のやりとりを聞く荒川アドバイザー(左写真の後方と右写真中央)
第7回 「アポロの月着陸を米国に取材して学んだこと ―『地球環境問題の大切さ』と『品質管理技術の大切さ』」
「有限である地球」を初めて実感させた映像―柴田鉄治さんが語ったアポロ報道 都丸亜希子(サポーター)
柴田鉄治さんの今回の話題は「アポロの月面着陸」。この時の報道が「科学の進歩が人類を幸せにするとは限らない」ことを世界中に認識させたという。残念ながら広島・長崎の原爆によってではなかった。なぜなら原子力でも「軍事利用が悪いのであって、科学技術が悪いのではない」というのが70年代までの一般大衆の思想だったからだという。
第二次大戦後、米ソはドイツの技術者を奪い合い、軍備拡張の一環として宇宙開発合戦を始めた。57年、ソ連が先に人工衛星を打ち上げ、スプートニクスショックを米国に与えた。対抗してケネディ米大統領は「60年代中に人間を月に到達させる」と宣言した。68年にアポロ8号が月から見た地球の姿を中継し、翌69年にはアポロ11号がついに月に着陸する。「宇宙に浮かぶ、かけがいのないオアシス」の地球を外から人類は見たのだ。
それまで先進国に個別には公害問題があったものの、その重大性に気が付いていなかった。アポロの運んだ映像によって、初めて「地球の有限性」や科学技術文明の問題に気づいた。69年はユネスコがアースデイ(地球の日)の概念を提起した年。72年には「かけがえのない地球」をキャッチフレーズとしたストックホルム会議が開催され、ローマクラブが「成長の限界」を発表するなど、この時期を境に地球環境問題が盛り上がっていく。
メディアはアポロ報道で地球環境問題に火をつけたと柴田さんは確信している。この時代を肌で感じた人だからこその洞察である。



第6回塾のようす(撮影:都丸亜希子)
■
歴史的「事実」と時代への想像力 =柴田鉄治講師の取材話を塾生と聞いて= 佐藤年緒(塾長)
1969年7月、アポロ11号の月面着陸を米国で取材報道した柴田鉄治さんの体験談を、世代が異なる塾生が聞く面白さがその日のテーマにあった。もう46年前の話なので、塾生の半分以上は生まれる以前の話、「歴史」の話である。元木さんが書いているように、テレビの映像で見たことがある、学校で習ったことがあるというメディアを通じた情報や伝聞なのである。
宇宙に浮く地球の写真は、いまでは教科書だけでなく至る所で見る。それだけに「当たり前」の地球の姿だが、50年近く前にその姿を初めて見た際の当時の人々の感動を現代の人がどこまで想像できるのか―そんなことを問う話題提供でもあった。
「地球が丸いことが証明できるのか?」という科学史上の論争も、アポロからの写真を見れば忘れてしまいそうな、映像にはそんな怖さもある。「本当は月面に着陸なんかしていない。テレビの映像のトリックだ」と「陰謀説」を取り上げたテレビ番組が米国と日本で放送されたこともあって、それを信じた若者がいることを柴田さんは大変気にしていた。歴史的な事実を当時の時代状況とともに想像する力が試されるのだろう。サポーターの都丸さんの記事も時代の背景を意識している。
それにしても、月面に初めて降り立ったアームストリング船長が発したとされる「一人の人間にとって小さな一歩だが、人類にとっては偉大な飛躍だ」という第一声は、米国の取材現場には伝わってこなかったと柴田さんは言う。東京の本社が米国の通信社を通じて得た情報だったとのこと。あらかじめ月に降り立った際に使う予定稿が通信社に渡されていたのではないか、本当に月面で発したのかと柴田さんは疑っているところが面白い。
私ごとだが、アポロ月面着陸の1969年の夏、私は浪人生だった。予備校のあったお茶の水界隈は大学が封鎖中で、学生による路上での投石が繰り返されていた。当時の私には月面着陸のニュースは何かよそ事のように響いた。アポロ打ち上げ寸前にケネディー宇宙基地に集まった黒人たちのデモ隊が「宇宙より地上の飢えを!」と叫んでいた動きを目撃し、特ダネにしたという柴田さん。当時、その社会面記事を読んでいたら、あすへの不安を拭えぬ私も共感しただろうが、残念ながら読み落としていた。
■
柴田さんが“抜かれた記事”にわくわく 元木香織(塾生・大学院生)
初めての月面着陸は1969年。そのころ私は産まれていなかった。しかし、いつどこでどのように知ったのか覚えていないが、月面着陸時の写真やアポロという名前、宇宙飛行士の名前を知っている。
1月27日の柴田講師の講義では、当時の取材の手法を切り口に、日本とアメリカの取り組み方の違いや、月面着陸成功の鍵を教えていただいた。また、地球がきれいな青色だったことが判明した途端に、地球上の人が環境問題を積極的に提起するようになった、という時代の流れの分析結果は面白かった。
とても印象に残ったのは、最後にお話された他の新聞社に“抜かれた記事”のこと。それはどこかで借りた宇宙服を着てみた体験を記事にした特ダネだった。その記者さんは、一足早くアツい情報をキャッチして企画したのだ。いま私が聞いても面白い!と思う。さまざまな切り口と斬新な企画でいくらでも面白い記事になるのだと分かり、書く仕事にわくわくした。
次の講義も楽しみである。しかしながら、私はこれから一ヶ月間の研究航海に出発する。塾を休むことになるが、目一杯、私の大好きな研究を楽しみたい。行ってきます!(1月31日、地球深部探査船「ちきゅう」でのインド沿岸調査航海出航を前に。筆者は横浜国大大学院環境情報学府修士課程1年)
8人の文を添削指導―武部俊一さんら 佐藤年緒(塾長)
科学ジャーナリスト塾の第6回講義は1月13日、元朝日新聞論説委員の武部俊一さんを講師に文章指導をしていただいた。塾生が新聞に投書することを想定して書いた文章に対する指導である。年末から出した課題だが、提出されたのは8人からだった。
その内容は、▽STAP細胞の有無論議がネット上で再燃、科学的な見方が大事(大学院生)▽駅トイレの臭い対策の在り方を問う(大学研究者)▽大麻解禁で犯罪率の増えた論拠がはっきりしない新聞記事(医学書編集者)▽学生が研究に見切りをつけざるを得ない現在の研究支援策(大学院生)▽新元素発見、夢を愚直に持ち続けた理研の森田さん(研究所広報)▽危うい日本のモノづくり(大学院生)▽法廷の映像記録を残そう(弁護士)▽旅情を損なう季節外れの商品広告(食品会社勤務)。
これらの原稿について武部さんは「完成度が高いとは言えず、このままでは載らない」として表現の工夫が要る箇所や言葉づかいの注意点を指導した。記事一つひとつについて塾生も意見を出し合った。塾生の1人は「課題文の添削だけでなく、他の塾生の方々のいろいろな考えも聞くことができ、非常に興味深いものだった」と振り返った。
塾生の大畑久美子(サントリー食品インターナショナル株式会社食品事業本部)は「武部さんが(新聞投稿の際に)大事なのは、素材・タイミング・レトリックだと締めくくったけれども、不特定多数の読者の関心をつかむために重要なこと。そこが学術論文やビジネス文書との大きな違いであると改めて気づかされました」という。さらに「印象的だったのが、『反論が起こるような文章の書き方もありだ』とコメントしたこと。共感であれ反感であれ、いずれにしても読者の心に刺さり、考察や議論の引き金となることがもっとも重要なのですね」と感想を述べた。
提出した塾生数は全体の半数以下だったが、「改めてお題に出されてみると、いかに自分が社会に言おうとしていることがないか苦心した」と話す塾生もいた。
8人の原稿に対する指導は、武部さんのほか、文章アドバイザーの漆原次郎さん、瀧澤美奈子さんもアドバイスを寄せ、執筆者に伝えた。




第6回の塾のもよう(撮影:都丸亜希子)
〔塾生の投稿記事から〕
研究を志す学生に支援を 遠藤智之(塾生・大学院生)
いま「理系」が危うい。次世代の担い手が育つ環境が整っていないと感じるからだ。自分を含め、研究を志していた同期の多くが、博士課程への進学をあきらめて、別の道を選んだ。文部科学省の調査では「望ましい能力を持つ人材が博士課程を目指していない」という研究現場からの認識が示されている。
待遇にその一因がある。欧米では、研究の担い手として、博士課程の学生に給与を支払うのが一般的だ。日本では、多額の学費と生活費の工面に苦しむひとが多い。国立大学の授業料が上がるという話も聞く。大学が国際化を謳う一方で、学生の懐を国際水準にするつもりはないようだ。
大学のキャンパスが、入試に臨む高校生で溢れる時期がやってきた。研究の道を志した数年前の自分を思い返す。ただでさえ、研究は茨の道だ。その道を選んだ若者たちを暖かく支援する国であってほしい。このままでは研究人材の枯渇は避けられない。科学技術の発展を担う「新芽」を摘む国に、科学技術立国を唱える資格はない。
■
法廷の映像記録を残そう 中道徹(塾生・弁護士)
テレビなどで裁判官や検察官、弁護士が座っている法廷の様子を見ることはあっても、そこに裁判員や被告人の姿はない。
彼らは、放送用のカメラが引き上げた後に入廷する。誰も彼らを撮影することはなく、映像は一切残らない。弁護士がどのような弁論や尋問をしたのかの記録も、一部音声テープが残るだけで映像としては残らない。手続の円滑な進行やプライバシーなどへの配慮がその理由となっている。
私は、この当然のように受け容れられている裁判の習慣に少し疑問を抱いている。歴史上、文字を持たない文明が後世において文字を持つ文明ほどの価値を置かれなくなったのと同様、法廷の映像が残らないのは、何か損失をもたらすのではないか、と。
ネットを中心に大量の映像が溢れ、車載カメラやドローンなどの技術によって今まで見ることができなかった映像を目の当たりにできるようになった現代、文字だけの情報では不十分に感じることが今後益々増えてくるであろう(実は、従前から、文字の記録が残っていても、「雄弁が聴衆に及ぼした効果ということになると、それを実証するものが、後に遺らない」などと言われていた)。
開廷前のわずかな時間のあの静謐、素早く立ち上がって大きな声でとなえられる弁護人の異議、弁解に首を捻る裁判員の挙動、繰り返しの尋問に憤慨して代理人を睨み付ける証人の様子などは、文字では決して伝えられないものだ。こういう映像が的確に記録されれば、将来、若手法曹の法廷での活動を錬磨するのにも役立つだろう。
撮影がなければプライバシーの侵害を防ぎやすくなるし、手続もスムーズに進むだろう。しかし、それによって、後世に記録を残すという面が犠牲にならないか。プライバシーの侵害などの懸念を予防した上で、法廷の映像記録を保存することもできるのではないか。我々は、これを考え始める時期に来ている。
第5回 「聴きだす力、伝える心 ―塾生を取材する、塾生が発信するために― 」
「番組をつくろう」と塾生参加の実演」―室山哲也さん 戸丸亜希子(サポーター)
第5回の塾(12月16日)では、NHKの解説委員・ディレクターである室山哲也さんを迎えた。テーマは「質問力」。初めに「僕はよく知らないのが武器。わかったふりをしない。本音でやる」。そして「僕がわからなきゃ、放送してもわからないだろう、と開き直っている」と質問力の大事さを説明しながら自己紹介した。
そして塾について「せっかく来たので学びたい、一緒に何か探ってみたい。結論が何か出るわけではないけれども、そのプロセスが大事かなと思うんですね」、「だから僕が喋ることのメモはしないでください」。つまり「番組作ってくださいってことやるんです」と宣言して講義に入った。
モノが語り出す
そんな室山さんからの宿題は「モノをつかって、あなたは何者ですかって、しゃべってほしい」である。次々に、そのモノを使った「魂の自己紹介」が繰り広げられた。
医療大麻に興味を持っている森永さんは「製麻」。研究のワクワク、ドキドキを伝えたい青木さんは「脳の画像」。ミクロの生物の世界の楽しみを伝えたい大崩さんは「虫眼鏡」。原発問題を扱う記者の山田さんは「福島のリンゴジュース」。科学で解決できないことへのモヤモヤをもっている堀川さんは「チンパンジーの子供の写真」。取材対象に憑依して疑似体験が楽しいという石塚さんは分析した「四重奏の楽譜」。昆虫の生態の研究をしている鈴木さんはきっかけになった「オオムラサキの標本」。留学先で覚え、これをつけていると覚えてもらえるし、怖い目にも合わないとう中道さんは「蝶タイ」。理系の大学院生から新聞記者に就職する遠藤さんは就活で集まった「50枚の名刺」。
「一点突破、全面展開」、「モノに支配されるのではなく、モノが一人歩きするような見せ方をする。そうするとモノがしゃべる」という。一点のシンボル。これは、その辺歩いていて見つけられる訳ではない。それなりの戦略があって、それにたどり着いていく、このプロセスがテレビ的なものだという。
異質な脳とのコミュニケーション
脳から脳へ伝わる。ここを忘れてはいけないという。どういうことか。これを体験するために、紙に「四角の上に三角を書く」という簡単な作業を塾生に行わせた。しかし、こんな簡潔な言葉を受けて書く図は、一つとして同じものが出てこない。それぞれの脳が世界を作っているのである。 さらに、牧野賢治さんをわずかな時間、正面に立ってもらった上で、塾生が記憶で描く「牧野さんの似顔絵」。各自の目を通過した情報は、脳でバラされ、もう一度まとめられて認識していることを実感した。都合よく情報が使えるように、脳が世界を作っているという。
視点が変わると違う風景が見えることを、隠し絵などで体感した。これらの作業の意味として、「異質な脳を持っている相手とコミュニケーションをやっているということ。これは認識しないとならない」と室山さんは強調した。「異文化衝突時代のジャーナリズムが求められているのは、自分の立ち位置。どこに立って、どこから何を見て、何を伝えるのか。周りばかり見ていると主張はなくなる。決して簡単なことではない」という。
なぜ、質問力なのか
「ジャーナリストの中で諸々ある基本的な能力の中で、一番大切な言葉をあげろと言ったら質問力」。なぜか?「質問をして何かを引き出す。だから、質問できるのかどうかはとても重要なこと」と室山さんはいう。「一緒に歩いた感じになって、最後に本質をついた質問が出てくると、相手は止まらなくなる」。つまり「その人とその場所で、何かについてやりとりして、初めて出てくる話が重要。場所が変われば違う答えになるかもしれない。だから、オリジナリティーがある」。そして「喋っている人も、あなたに聞いてもらえてよかった、そうだったよ、俺も忘れていたよ。そういう感じのインタビューがいい」とヒントを塾生に与えた。
さらに先ほど登場した牧野さんへの質問コーナー(答えはなし)。最後は福島のジュースを題材とした山田さんの話で、番組を作るための質問練習となる。オンエア2分前として、議論は打ち切りられ、塾生はストーリーの骨格を書かされ、室山さんの一人芝居のカウントダウンが始まった。「5秒前、4、3、2、1。はいスタジオに入ってくださーい、オンエアでーす。今日の話はここまで」と講義は終了した。拍手のあと「今のはね、プロセス。自分の頭の中で、うわーっとなったプロセスが大切。それを覚えておいて」とアドバイスの一言が入った。





第5回塾のようす(撮影:都丸亜希子)
【補足】
この日塾に特別参加し、塾生の似顔絵の対象とされたり、質問相手にされたりした牧野賢治さんからは、ご自身の著書である『科学ジャーナリストの半世紀―自分史から見えてきたこと』(化学同人)が塾生全員にプレゼントされました。ここにお礼申し上げます。(この項、佐藤年緒記)
第4回 「南極観測隊に同行取材して学んだこと ―『国家とは何か』『科学の国際協力とは何か』」
2015年12月2日(水)の科学ジャーナリスト塾では、科学ジャーナリストの柴田鉄治さんが「南極観測隊に同行取材して学んだこと ―『国家とは何か』『科学の国際協力とは何か』」というテーマで話題提供し、塾生たちが議論を深めました。塾生の石川航平による報告記事と、佐藤年緖塾長による補足記事をご覧ください。
■
科学ジャーナリストが「南極で見たもの」 石川航平(塾生)
12月2日の科学ジャーナリスト塾の第4回講義では、科学ジャーナリストの柴田鉄治さんによる南極取材の経験談をうかがった。朝日新聞社の科学記者として2度南極観測隊に同行、南極に魅了されて退職後も3回訪れたという。「長年の積雪によって極点の標高は2800メートルにもなる」など、南極の自然や観測の歴史、取材の話をスライドで説明。塾生も初めて聞く世界に驚いた様子だった。
柴田さんは、国境もなく国を超えて協力し進める南極観測の取材体験から、「国家とは何かを考えざるをえなかった。地球から貧困や紛争、また戦争が生まれることは、あくまで人間が引き起こした人間自身の問題ではないか?」と深い問いを投げ掛けた。
塾生は熱心に耳を傾け、次々と質問が続いた。ジャンルは国際政治、スポーツや気象など多岐に渡った。印象に残ったのは「ジャーナリズムとして発信する上で事実をどう捉えるべきか?」という質問だった。それに対して柴田さんは記者としての心構えをこう語った。
「取材した事実は書けるものの、国境のない世界が理想の世界だ、といった主張を新聞社に在籍している時は書けなかった。フリーになってからの講演会では何十回と話し続けることで、きっと次の世代が私の意思を受け継いでくれるはずです」
このほか塾生から「南極に原発があるという事実に衝撃を受けた。環境や国際政治の問題など、社会のテーマに関心が広がった」という感想も聞かれた。
柴田さんはこう締めくくった。「南極はいかに素晴らしいか、その思いを伝えたかった。いっそのこと国境をなくして“地球国家”という一つの国にすれば良い。『南極は地球の憲法九条だ』ということです」
最後に柴田さんが作詞をした「南極賛歌」に作曲家の池辺晋一郎氏が曲を付けた混声四部合唱曲『地球の九条もしくは南極賛歌』が合唱団によって歌われている映像が紹介された。
[参考]合唱曲はインターネットで以下の記事を引くと映像とともに聴けます。 朝日新聞デジタル「南極と9条つなぐ平和の賛歌 25日に調布で披露」(2015年1月21日)http://www.asahi.com/articles/ASH1J5VD3H1JUUPI001.html
■
南極と柴田鉄治さん 佐藤年緖(塾長)
「中学生のころから科学者になるのが夢だった」という柴田鉄治さん。湯川秀樹博士のノーベル賞受賞のニュースに感動し、自然界の道理を解き明かす仕事に憧れを抱いたという。大学では地球物理学を専攻。壮大な宇宙の謎、そのなかの惑星の一つ、地球の謎に挑んでみようと考えた。柴田さんがなぜ、いまも南極を伝え続けているのだろうか。
▽戦争体験も重なって
柴田さんが大学生だった1956年に、日本の南極観測が始まった。第1次観測隊が帰国した直後の大学の「五月祭」に、「南極観測の展示をやろう」と展示物集めに走り回った。朝日新聞社に写真を借りに行ったのも、その時が初めてだった。
科学者への夢を捨てて新聞記者になったきっかけは、大学にあるジャーナリズムの研究機関の「新聞研究所」の教育部が公募した学生活動に参加したことだ。新聞社のOBたちの語るエピソードは痛快だった。あの戦争を止められなかったのは戦前の新聞がジャーナリズム精神を失い、「死んでしまったからだ」という真面目な話は、子どものころの学童疎開や東京大空襲の体験などから「二度と戦争はごめんだ」と思っていた柴田さんの心にしみた。
「ジャーナリズムの仕事も面白そうだなと思った。そのうえ新聞社が南極観測を提言し、実現させることもできるのか、という思いが背中を押してくれた」と振り返る。
記者になって3年目、札幌に勤務していたとき、無人の昭和基地で1年間、奇跡的に生きていたカラフト犬のタロ、ジロのうち、タロが札幌に帰ってきた。観測船「宗谷」も南極での役目を終え、巡視船として北海道に戻ってきた。オホーツク海での流氷調査に乗船して連載記事を書いた。
▽惚れ込んだ「理想の地」
そんな縁があって、東京の社会部に転勤した1965年、完成した新砕氷船「ふじ」で再開された南極観測(第7次観測隊)の同行記者に選ばれた。30歳のときだった。
その取材で柴田さんは南極に心底から惚れ込んでしまった。人類にとって「理想の地」だとの思いは、それ以来ずっと抱き続けている。新聞記者生活も終わり、大学での客員教授の仕事も終わって、自由な時間ができたとき、「もう一度、南極へ行こう」と思い立った。そのときは70歳。
帰国後、「南極の語り部」として南極の素晴らしさ、とくにその平和な姿の伝えようと「南極条約」(1961年発効)を紹介するなど、あちこちで講演活動を続けてきた。あるとき、講演を聴いた友人から「きょうの話を『詩』にできないか」という話が舞い込んできた。出来上がった詩がこの『南極賛歌』だ。
1、 南極は 地球の九条だ
国境もない、軍事基地もない
人類の 理想を実現 平和の地
2、 南極は 素敵な自然の楽園だ
ペンギンがいる アザラシがいる
生き物が 共存共栄 豊かな地
3、 南極は 宇宙に開く地球の窓だ
オーロラがある 隕石がある
なぞを解き 未来をさぐる 科学の地
4、南極は、地球環境のモニターだ
氷を掘る オゾンを測る
力を合わせ 環境守る モデルの地
5、南極は 地球の憲法九条だ
戦争なくし 人類仲良く
世界中を 平和に変える 魔法の地
▽合唱曲として、「南極授業」として
詩は友人を通じて作曲家池辺晋一郎氏に届けられ、ざっと7年が過ぎた2014年春、「実に実に遅くなりました」という手紙とともに池辺氏から混声四部合唱曲の楽譜が届いた。池辺氏は「音楽九条の会」の呼びかけ人でもあり、「世界平和アッピール七人委員会」の委員でもあった。合唱曲名は『地球の九条もしくは南極賛歌』とされたが、南極にも、憲法九条にも「ほれ込んでいる」柴田氏は反対する理由はないという。
こうして2015年1月25日、調布市グリーンホールで開かれた「池辺晋一郎さんと平和を歌おう」という催しの中で、池辺氏指揮による調布合唱団の合唱が披露された。柴田さんは「それを聴いて私がどれほど感動したことか」と話す。
そしていま柴田さんは「南極の素晴らしさを子供たちに伝えたい」と次世代を担う子供たちの教育にも関心を向けている。全国の小・中・高校の教員を南極に派遣するプロジェクトをスタートして7年。ネットワークの連絡役を担い、今年の年賀状でも「南極授業を全国の学校に広げていくためにご支援を」と呼び掛けた。
11月18日の第3回塾は、実践演習の日。高橋真理子・朝日新聞編集委員が「記事/報告文の書き方」をテーマに文章指導をしました。あらかじめ塾生に示した課題である「私が受けた作文教育」についての文が12人の塾生から提出されたことから、これらを皆で読み合いました。
高橋講師はエッセイと報告文との違いや、報告文に必要な要素などについて解説。12人の文を塾生らとともにコメントしました。どの文を読んでも、日本の学校教育のなかで体系だった報告文の教育は受けていないことを伝えています。以下3作品は、個人がどのような努力や工夫、苦労をしながら、文章の技を習得してきたかを物語っている貴重な記事だと評価して、ここに紹介します。
〔塾生の投稿記事から〕
英語・論文・読書感想文 大崩貴之(塾生)
作文と聞いて真っ先に思い出すのは小学校の読書感想文である。しかしそれは宿題として与えられるもので、書き方を習うわけではない。感想を書き連ねるだけの作業に意味を見出せず、前書きと後書きだけを読んで適当にまとめたのを覚えている。作文の教育という点では、文法などの言語学の基礎は中学校の英語の授業、作文技術そのものは大学院での論文執筆が私にとって大きな糧となっていると思う。
日本語に囲まれて育った私は、当然のように日本語を話し、読み書きができるようになった。特に文法などを意識したことはなかったが、それで困ることもなかった。事情が変わったのは英語の勉強を始めたときである。主語や動詞といった、それまで意識しなかった文を構成する要素の存在をそこで初めて学んだ。比較する対象ができるとそれまで当たり前に使っていた日本語を客観的にみることができ、主語が省略されるといった日本語の特性も理解することができた。
とはいえ、作者の意図だけ読み取れれば困らない環境で大学まで過ごしてきたため、作文の仕方を本格的に意識する必要が出てきたのは論文執筆を始めてからである。論文は客観的事実とそこから導かれる論理的帰結だけを記す場なので、曖昧な表現が多いと言われる普段使いの日本語感覚で書くと誤解が生じやすい。論文に求められるような、事実と解釈を区別することや、根拠を引用することなどの諸規則を指導教官の指導のもと実践の中で学び、今に至る。
私の作文能力の背景は英語と論文にあるが、文章を書くという行為には様々な目的があり、それに合わせて手段も変えなくてはならない。科学的主張を論理的に述べることだけが作文ではないことは、市民向けコラムなどを執筆するようになって改めて理解した。目的に応じた様々な方法で文章を書くことの大切さと難しさを実感するようになった今になって、読書感想文も真面目に取り組むべきだったと反省してもしきれない。
■
私の文章修行 青木田鶴(塾生)
私の文章の師は、児童文学作家だった母である。文章にこだわる母と根っから議論好きな父の教育方針は変わっていた。たとえばマンガ3原則:マンガは買わない、借りない、持ちこまない。テレビは土曜日の決まった番組だけ。私たち4人姉妹は友人との隔たりにいつもため息をついていた。中でも異色だったのが、ことあるごとに書かされた作文だ。読んだ本の感想、旅行記、創作、それから叱られた後の反省文。
4人も子どもがいれば毎日必ず何かが起こる。妹とけんかした、頼まれた手伝いをしなかった…ただ謝るのではなく、何が起こり、何が悪かったのか、これからどうするのか、両親に説明しなければならない。それが終わると母は「書くよ」と鼻息も荒く、原稿用紙と鉛筆を持ってくる。「自分が何をして、何を考えたのかをまとめる!原稿用紙3枚まで!」
書き上がると赤が入る。「てにをは」から表現まで細かく直され、直しが2度3度に及ぶことも珍しくなかった。書いた文は著作権も個人情報の保護も無視され、担任の先生の手に渡ることもあった。これは中学生まで続いた。
高校に入ると、母は作文指導をぱたりとやめてしまった。代わりに母は、読者としての批評を求めて、自分が書いているものを私に読ませた。私はいわば母のお抱え編集者だった。時間をかけて入れた赤を、母が採用してくれることが嬉しかった。
研究の道へ進んでからは学術論文や申請書の書き方を学んだが、小手先の技術を習得しただけで教育を受けたという意識はない。プレスリリースも同じだ。幼い頃の修行で、書くことの基本が身についたといっても過言ではない。
母は2年前に肺がんで亡くなった。抗がん剤の治療でぐったりしていても、童話のプロットの話をするとみるみる元気になった母。次の日には原稿用紙に向かっていた母。それを最期の作品に仕上げた母。思い出す度に、書くことの意味、書くことが人に与える力を、私は再確認する。
■
分かりやすく魅力的な文章を書くために 鈴木紀之(塾生)
思えばロクな作文教育を受けてこなかった。小学生の頃は「起承転結」とよく言われたが、この流れを意識して文章を書く機会がほとんどない。
自分の作文能力が上がったと思えたのは、いくつかの良著のおかげだった。
日本語のスタイルに関しては、『日本語作文の技術』(本多勝一著)が必読だろう。特に、「語句を並べる順番」と「読点を打つ位置」はすべての日本人が知っておくべきスタンダードである。
残念ながら、私がこの本を読んだのは大学院を修了してポスドクになってからのことだった。もっと早いうちに読んでおきたかった。著者が述べているように、初等教育の段階でこれらの法則を学ぶべきである。
文章どうしのつながりや段落の構成に関しては、『書く技術・考える技術』(バーバラ・ミント著)が参考になった。特に、ストーリーの導入部(科学論文で「序論」に該当する部分)についての解説は秀逸であった。このルールさえ守っておけば、「分かりやすく伝える」という点では間違いないだろう。
しかし、「分かりやすさ」の先にある「より魅力的な文章」の書き方について、私はまともに学んだことがない。
サイエンスライティングでは、ストーリーの冒頭にキャッチーなエピソードを挿入し、読者をぐっと引きつける技法がよく使われているようだ。読者が共有する常識や一般論から始まる科学論文とは異なり、いかにリード文を魅力的に書くかが鍵となる。
それは、「分かりやすい構成」を崩すからこそ、ひと際目立つ存在になるのだろうか。それとも、その「崩し」はすべての文章が採用すべき技法、すなわち「文章の法則」になりえるのだろうか。体系的な考察が欲しいところだ。




第3回の塾のもよう(撮影:都丸亜希子)
第2回 「歴史を記録する―科学ジャーナリストのもう一つの役割」
第14期科学ジャーナリスト塾 第2回(2015年11月4日)で塾生が挑んだ課題「第2回塾の内容レポート」の中から4点を掲載します。
〔塾生の投稿記事から〕
「真実を後世に伝える」志で歴史を記録する 大畑久美子(塾生)
11月4日夜、プレスセンタービル内の会議室にて、第2回科学ジャーナリスト塾が開催されました。この日の話題提供者は、北村行孝先生。読売新聞社会部、科学部を経て、論説委員や科学部長などを歴任されたご経験をお持ちです。
会合の前半およそ1時間弱の間、北村先生が出版された書籍『日航機事故の謎は解けたか』を題材に、執筆の経緯や背景についてお話ししました。この回のテーマとして「歴史を記録する」というタイトルが掲げられていた通り、事実を記録し後世に残すというジャーナリストの使命について、ご自身の体験談を交えてお話くださり、塾生たちは熱心に耳を傾けていました。
また、「事故調査」と「捜査」の違いについても言及し、責任の訴追よりも原因究明と再発防止に重点をおく「事故調査」の在り方についての課題も示されていました。
北村さんのお話しを通じて感じたことは、「真実を伝えることの難しさ」です。歴史を記録し正しく伝えていくためには、多面的に様々な情報を収集した上で、主観に拠り過ぎず客観的な視点で文章を構築していく必要がありそうです。そのためには、テクニカルなスキルも求められますが、やはり「真実を後世に伝える」という志が重要なのではないかと思いました。
また、「誰のためのジャーナリズムか」という思いも自分の中に生まれました。事実を伝えることが、どのような人のどのような幸福につながるのか、あるいは世の中のどのようなところでどのような発展に貢献できるのか…今まで考えてもみませんでしたが、これからは常に自分に問い掛け続けたいと考えています。
話題提供の後は、塾生同志が顔を突き合わせて各々の考えたところについて意見を述べ合い、最後に各グループで出た意見を全体で共有しました。このように他の塾生と意見を交換することで、お互いに考えを深めていくことができたと思います。
■
取材メモの蓄積がものをいう 石塚集(塾生)
隔週の水曜日、プレスセンタービルにて科学ジャーナリスト塾が開催されている。科学ジャーナリスト塾では、日本科学技ジャーナリスト会議(JASTJ)会員の記者が中心となり、科学技術の伝え方を塾生に教えている。11月4日の2回目では、読売新聞社会部・科学部OBで、現在は東京農業大学教授である北村行孝さんから、著書『日航機事故の謎は解けたか』(2015年発刊)を軸に、ジャーナリズム全般に関する話があった。そこで強調されたのは、取材メモを大切にとっておいたことが歴史を正しく伝えるのに役立ったということだ。
この著書のテーマは1985年に起きた日航機123便墜落事故だ。飛行中の航空機事故では最大となる520名の犠牲者が出た。
北村さんは事故から30年経って書籍を発刊した思いをこのように語った。「私の記者人生の中で一番大きな事件だったし、関わりが非常に大きかった。そして当時は様々な事情で語れなかった人たちがようやく語りだした。長い目で案件を見ることで、当時とは違ったものが見えてきた」。
さらに、北村さんは取材メモに関して「入社した時に、先輩から取材メモは捨てるな。大切にとっておけと言われた。はじめは訴訟対策のためと思っていたけれど、新たな書籍の発刊にも結び付くような効用がある」と塾生に熱っぽく語った。これには塾に同席していたジャーナリスト経験者たちも同調して、メモをとっておくことの重要性を強調されていた。その場のいた証人として歴史を正しく伝えるためには、客観的なものはできるだけ残しておくことが大切なのだと改めて肝に銘じさせられる話だった。
塾生同士の議論で話題になったのは「ジャーナリズム」の語源だった。北村さんからは「ジャーナル」はラテン語で「一日の」を意味すると説明 があった。これに「主義」などの意味の「イズム」がついて「ジャーナリズム」になったわけだが、ジャーナリズムとはどんな立場か、記事は主観 と客観どちらでかかれるべきものなのか、そもそも客観は存在するのかという話題で盛り上がった。この論点は塾を通して皆が、自分の立場を明確 にしながら考え続けることになるだろう。
■
歴史のデッサンから絵画へ 遠藤智之(塾生)
第2回の塾は読売新聞科学部OBの北村行孝さんを招き、「歴史を記録する-科学ジャーナリストのもう一つの役割」をテーマに開いた。北村さんは新聞記者として日本航空123便御巣鷹山墜落事故を担当。関係者への取材を重ね、5年後には経緯を1冊の本『日航機事故の謎は解けたか』にまとめた。事故から30年経った今年、事故の資料と関係者のインタビューをまとめた書籍を出版した。改めて出版するに至った想いを聞いた。
新聞社を退社後、北村さんは事故の関係者を訪ねた。当時、事故原因の究明を担った事故調査委員会の委員などだ。関係者も高齢になり、事故資料を多く抱えているが、その扱いに悩んでいた。「消えてしまうかもしれないものを残したい」との想いから、北村さんは出版を決意したという。当時、調査委員会の関係者は調査の経緯を外部に話せない。事故調査の独立性を確保して、正直な証言をしてもらうためだ。今回の本では、当時書けなかった名前や実名インタビューを掲載できた。30年という時間の経過がそれを可能にしたという。
取材テーマは決められており、眼前のニュースを追うことで精一杯のはずだ。だが、「時事刻々の変化を追う以外にも勝負どころはある」「インターネットがある今、メディアは確実性を重視すべき」と北村さんは語る。情報が氾濫する現代、日々の出来事を伝える以上の役割がメディアに求められていると感じる。長期的な視点であるテーマを掘り下げ、少し後になってからでも、仔細を伝えることが必要なのではないか。今回のように書籍も一つの方法だ。加えて、新聞であれば解説記事の重要性と需要が増すだろうと思う。
記者は「歴史をデッサンする」仕事であると聞いたことがある。今回の塾では、デッサンから一枚の完成した絵画を描くまでを学ぶことができた。私は来春から新聞記者となるが、これから取材を進める中で、自分なりの問題意識を形成して、一つのテーマについて長期的な視点で追いたいと思う。
■
30年後の記事に救い 山田理恵(塾生)
発生から30年経つ事故について改めて記事を書く意義は何か。520人の犠牲者を出した日航機の墜落事故を取材した元読売新聞記者、北村行孝さんが11月4日、そんなテーマについて講演した。お話を聴いて、救われた気がした。同じ記者として、事故を書き捨ててこなかったかの思いを重ねた。
北村さんは今年、『日航機事故の謎は解けたか 御巣鷹山墜落事故の全貌』を出版した。きっかけは2010年、退社のあいさつで遺族や事故の調査関係者に会いに行ったことだった。
彼らの中には資料を整理して残している人や「教訓を残したい」と漏らす人もいた。一方、世間には隕石やミサイルで爆破されたといったうわさもいまだに残っていた。「航空機史上最悪の事故をもう一度きちんとまとめたい」という思いが募ったという。
北村さんは残していた段ボール2箱分の取材メモや資料を手に、改めて関係者を回った。事故からの長い歳月は、予想以上に取材を後押しした。警察や調査担当者は現役を引退し、当時よりずっと取材に協力的だったという。
新聞社に勤め、交通事故や殺人事件、大災害を取材することもあった。まだ悲しみにくれる犠牲者の遺族に会いに行き、つらい経験を語ってもらい、記事にした。私は転勤すれば、また新たな取材に追われる。一方、遺族にとって悲しみはずっと続く。自分が遺族の思いを「消費」しているような気がして罪悪感が募っていた。
事故から30年後に改めて記事を書くことについて、北村さんは「遺族は長い歳月が過ぎると、(事故を起こした当事者への)処罰より教訓を残したいと思うようになる」と語った。事故当初の遺族の思いを報じるのも大切だが、歳月とともに変化する遺族の思いに改めて向き合うことも、ジャーナリストの役割だと感じた。


第2回の塾のもよう(撮影:都丸亜希子)
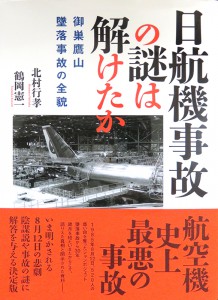
北村講師の共著書『日航機の謎は解けたか』
第1回 ガイダンス「塾で学んだこと、学ぶこと―体験を未来に」
第1回の報告 柏野裕美(サポーター)
2016年10月21日に第14期科学ジャーナリスト塾が始まりました。塾生にはジャーナリストやライター、学生、公務員、会社員など、多彩なメンバー19人が集まりました。それぞれ科学をいかに伝えるかについて課題を持ち、解決するために参加を決めたといいます。
冒頭、佐藤年緒塾長があいさつし、この塾は14年前に科学技術の伝え方を所属組織や職種を超えて学び合うための場として 立ち上げた経緯を説明。続いて、塾生の自己紹介では、幅広い科学の世界でも各々が所属する分野や仕事をする上での視点から、または消費者の立場からの考え方や抱負などが語られました。
塾生の中には、「自分は飽きっぽいかもしれない」とか「自ら学ぼうという意識より友人から『入れ』と言われて入った」といった発言もあって、場を和ませました。皆の自己紹介を聞いていると、 個々の人が「科学コミュニケーション」をテーマに、この場でつながる様子が、故Steve Jobsの言葉として知られる”Connecting the dots”のようでした。
司会の藤田貢崇事務局長をはじめ、運営スタッフ、文章アドバイザー、サポーターも次々にあいさつ。12、13期の塾生だった私の経験からは、初対面の人の顔と名前が一致するのは、塾の終了間近になる心配もある。であれば小出重幸会長が言われたように、塾の放課後の集いに参加するのも塾を楽しむ方法と言えるかもしれません。
次の開講日は11月4日。『日航機事故の謎は解けたか』を出版し、塾生にも配布くださった北村行孝さんが話題提供をされます。

テーブルを囲んで始まった第14期の科学ジャーナリスト塾
第14期 科学ジャーナリスト塾
→塾生の募集は終了しました。ご応募ありがとうございました。
2015年も10月から半年間、科学ジャーナリスト塾を開催します。ここで学ぶ人が、科学ジャーナリズムの精神と方法を学び、自らが記事を書いたり表現したりすることに、日本科学技ジャーナリスト会議(JASTJ)の会員が応援、指導する塾です。科学や技術に関してのテーマについて過去や現在、どう伝えているか、その体験や考え方、方法を伝える塾です。塾生自身も発信する訓練の機会を用意します。「体験を未来に生かす」テーマの下に意欲のある塾生の参加をお待ちしています。
新聞社やテレビ局などで活躍した経験豊富な人たちが「話題提供」する現代的なテーマについて塾生とともに論議し考えるほか、書き方や取材の仕方などの「実践方法」を織り交ぜながら、計10回にわたって塾を展開します。自ら書く機会も設け、それに対するコメントなど指導を受けられるほか、JASTJの月例会での講演のレポート書きに挑戦もできます。 主な内容は以下の通りです。(20151002現在)
- 第1回 10月21日(水)午後7時~9時 塾の開講 ガイダンス「塾で学んだこと、学ぶこと―体験を未来に」 小出重幸JASTJ会長 佐藤年緒ら塾関係者・サポーター、塾OB/OG
- 第2回 11月4日(水)歴史を記録する―科学ジャーナリストのもう一つの役割 北村行孝(東京農業大学教授、読売新聞社会部・科学部OB)
- 第3回 11月18日(水)記事/報告文の書き方 高橋真理子(朝日新聞編集委員)
- 第4回 12月2日(水)南極観測隊に同行取材して学んだこと ―「国家とは何か」「科学の国際協力とは何か」― 柴田鉄治(元朝日新聞科学部長・社会部長)
- 第5回 12月16日(水)聴きだす力、伝える心 ―塾生を取材する、塾生が発信するために― 室山哲也(NHK解説委員)
- 第6回 1月13日(水)塾生の「投書欄」記事を読んで 武部俊一(元朝日新聞論説委員)らアドバーザー
- 第7回 1月27日(水)アポロの月着陸を米国に取材して学んだこと ―「地球環境問題の大切さ」と「品質管理技術の大切さ」― 柴田鉄治(元朝日新聞科学部長・社会部長)
- 第8回 2月10日(水)地球温暖化問題をどう伝えるか 横山裕道(淑徳大学客員教授、元毎日新聞論説委員)
- 第9回 2月24日(水)現場でしか見えない原発被災―福島で伝えること 上田俊英(朝日新聞編集委員)
- 第10回 3月9日(水)未来に向けて―まとめ 塾生の文を見て伝えたいこと(漆原次郎JASTJ Web編集長。高木靱生JASTJNews編集長)、未来世代に送るメッセージ(小出重幸会長、林勝彦理事)、アドバイザー、サポーター、塾生OB・OGより(柏野裕美、都丸亜希子など)
■期間
原則第1,3の水曜日午後7時~9時。計10回
10月21日、11月4日、18日、12月2日、16日、1月13日、27日、2月10日、24日、3月9日
■場所
プレスセンタービル8階特別会議室(千代田区内幸町2-2-1)
■塾受講料
通期1万6000円(10月末日締め切り)
■話題提供者(講師)
室山哲也(NHK解説委員)、北村行孝(東京農業大学教授、読売新聞社会部・科学部OB)、柴田鉄治(元朝日新聞科学部長・社会部長)、高橋真理子(朝日新聞編集委員)、上田俊英(朝日新聞編集委員)、横山裕道(淑徳大学客員教授、元毎日新聞論説委員)、小出重幸(JASTJ会長、元読売新聞科学部長)、佐藤年緒(「Science Window」編集長、元時事通信編集委員)、林勝彦(元NHKプロデューサー)
■文章アドバイザー
小出重幸、武部俊一(元朝日新聞論説委員)、瀧澤美奈子(サイエンスライター)、漆原次郎(JASTJ Web編集長)、高木靱生(JASTJ NEWS編集長)、高橋真理子、浅羽雅晴(元読売新聞編集委員)
■申し込み方法
希望者は、氏名、所属(または職業)、住所、連絡方法、メール、電話番号のほか、参加動機(400字程度)を書いて塾事務局宛て(juku-office@jastj.jp)にお送りください。10月20日(火)まで。塾生の人数が定員(20人)で締め切ります。
■申し込み・問い合わせ先
塾事務局(juku-office@jastj.jp):
塾長・佐藤年緒、副塾長・西野博喜、JASTJ事務局長・藤田貢崇
(2015.09.29)




