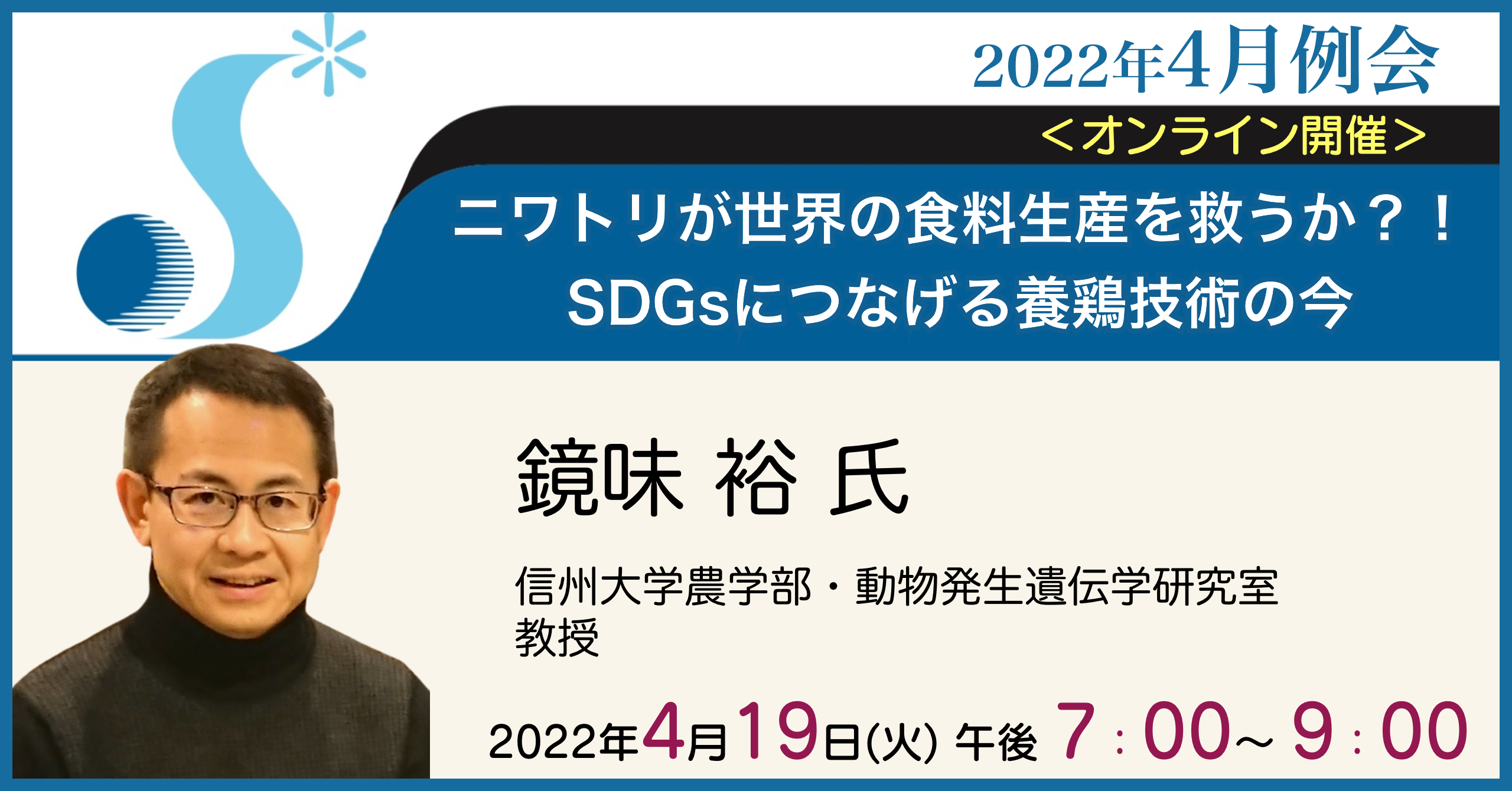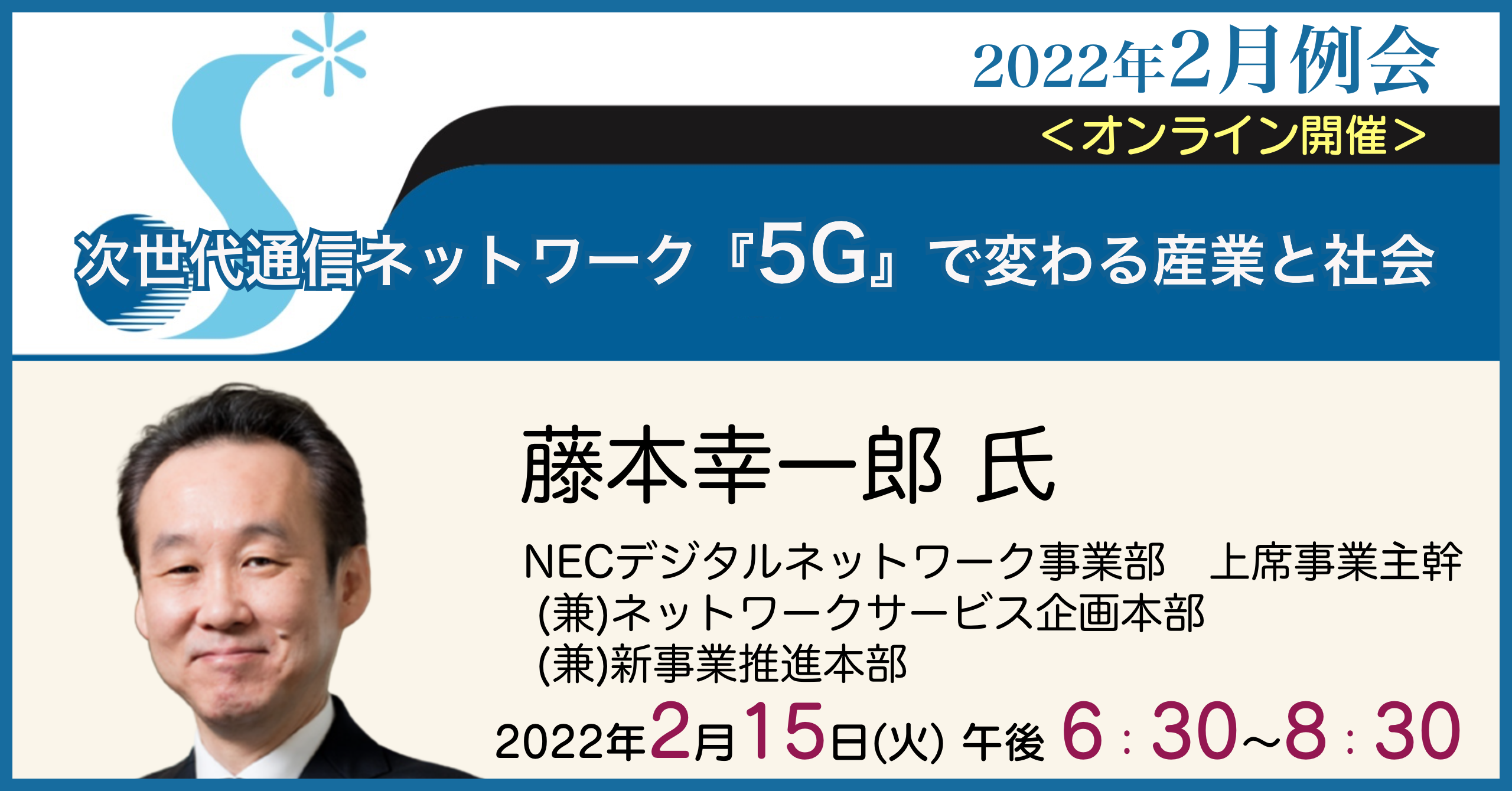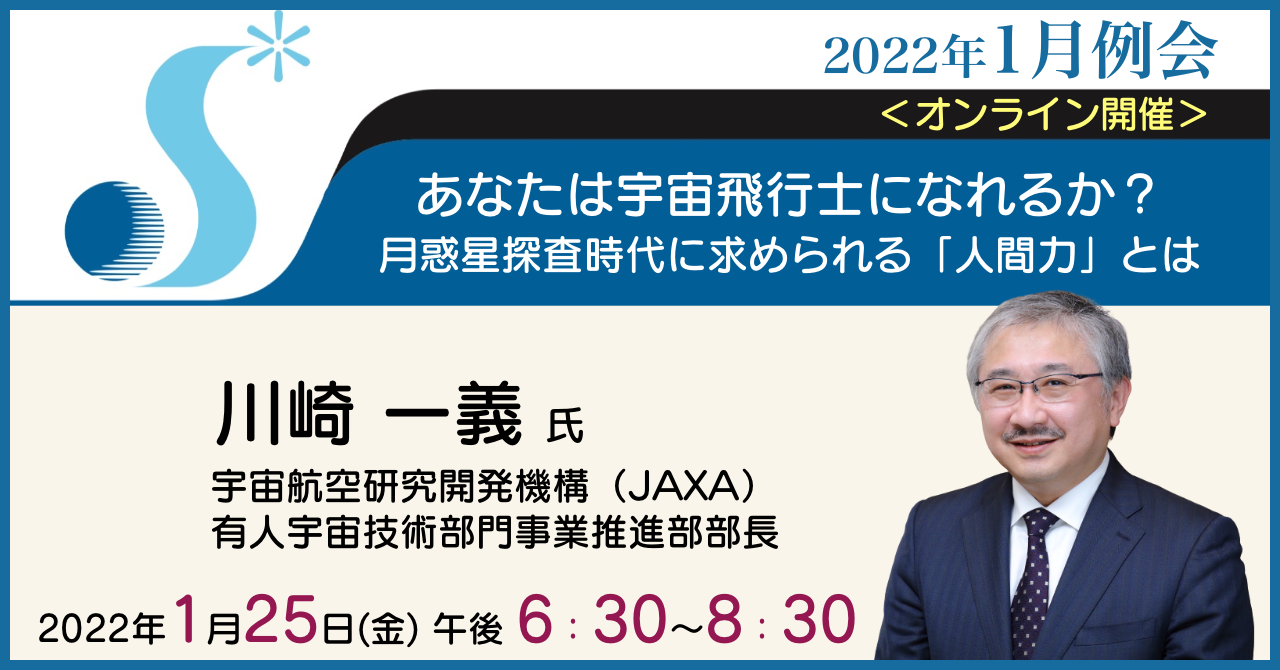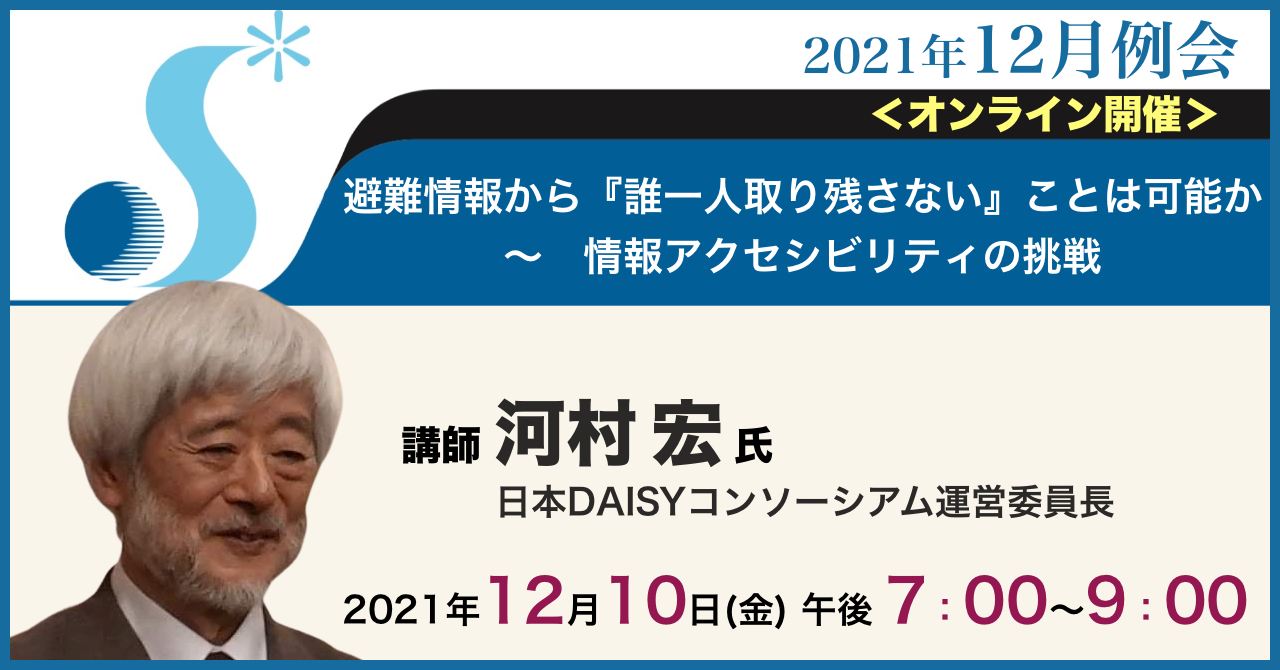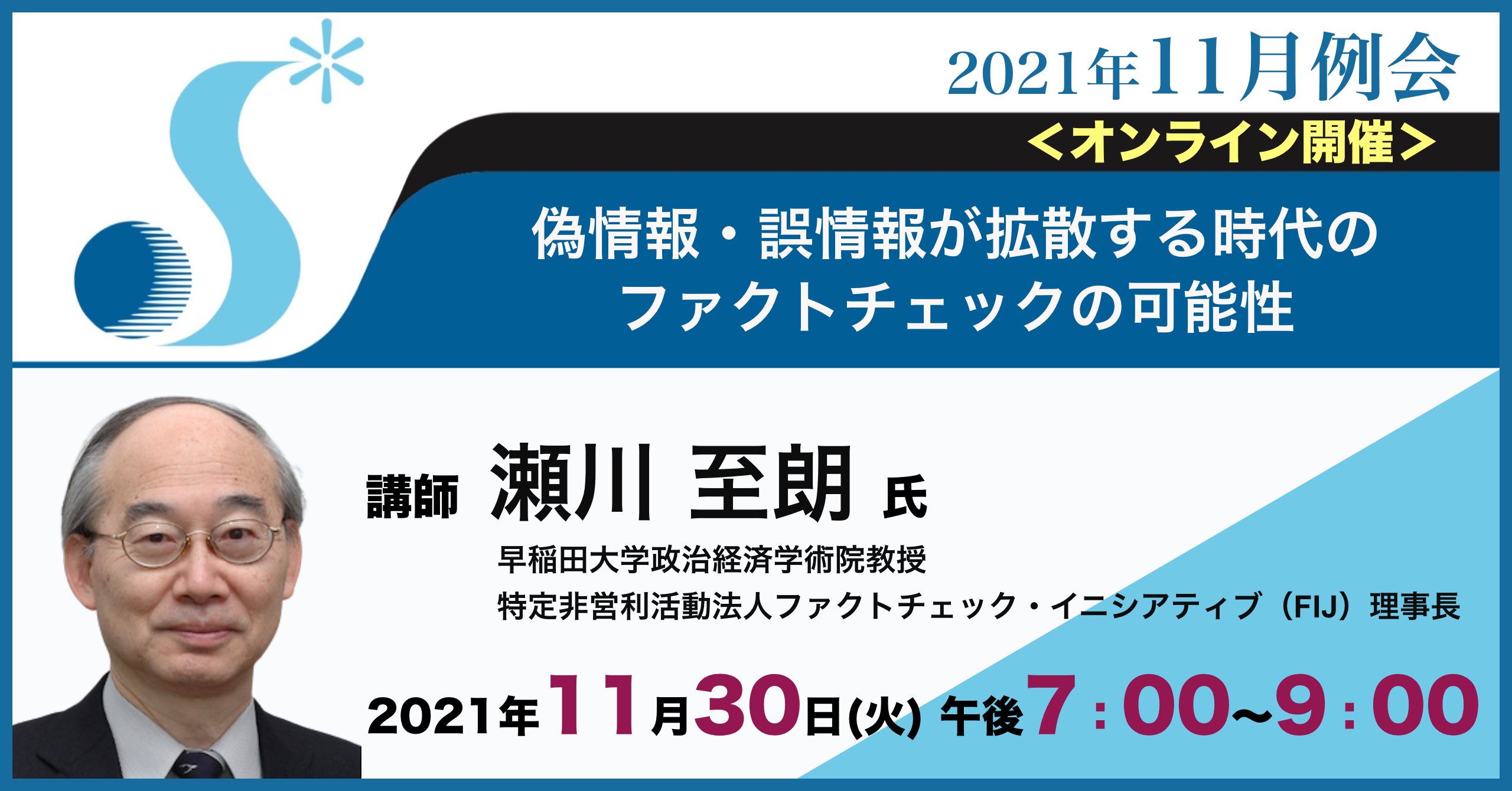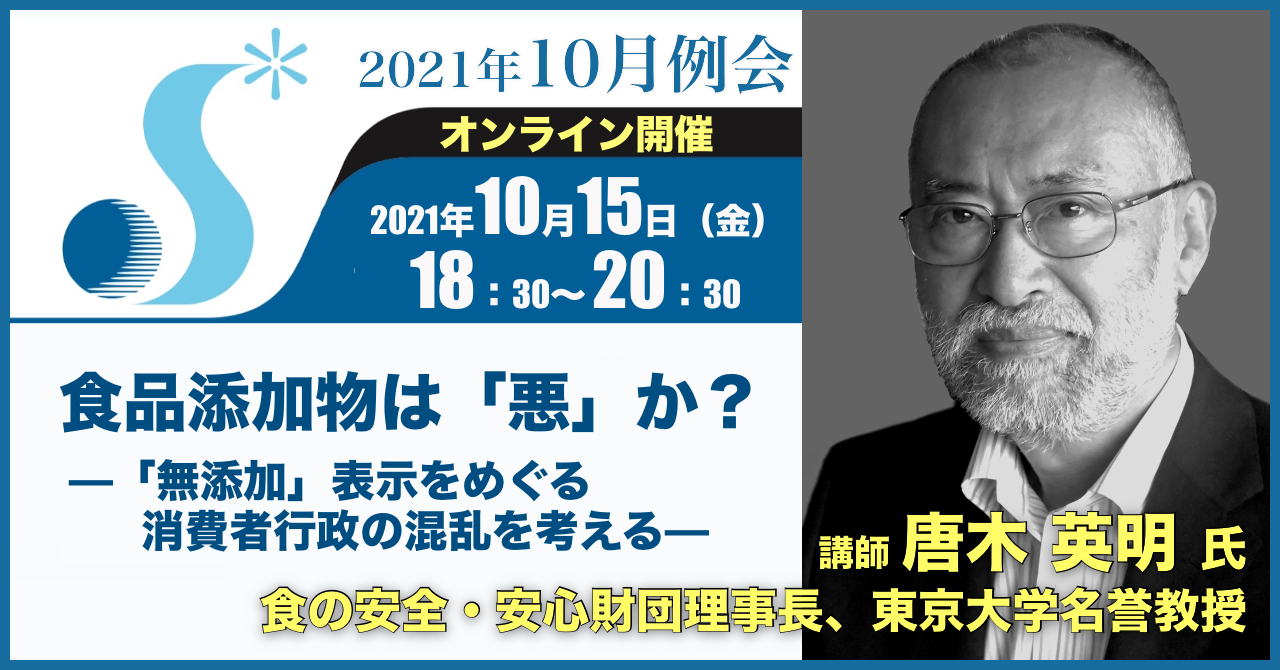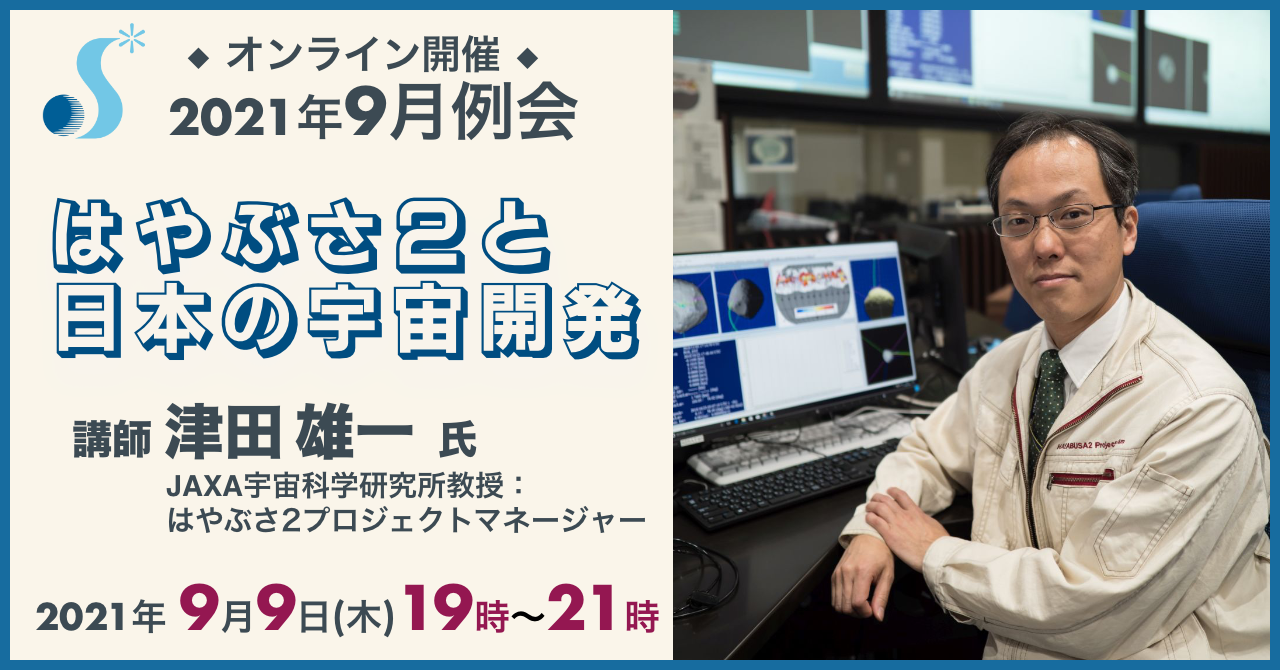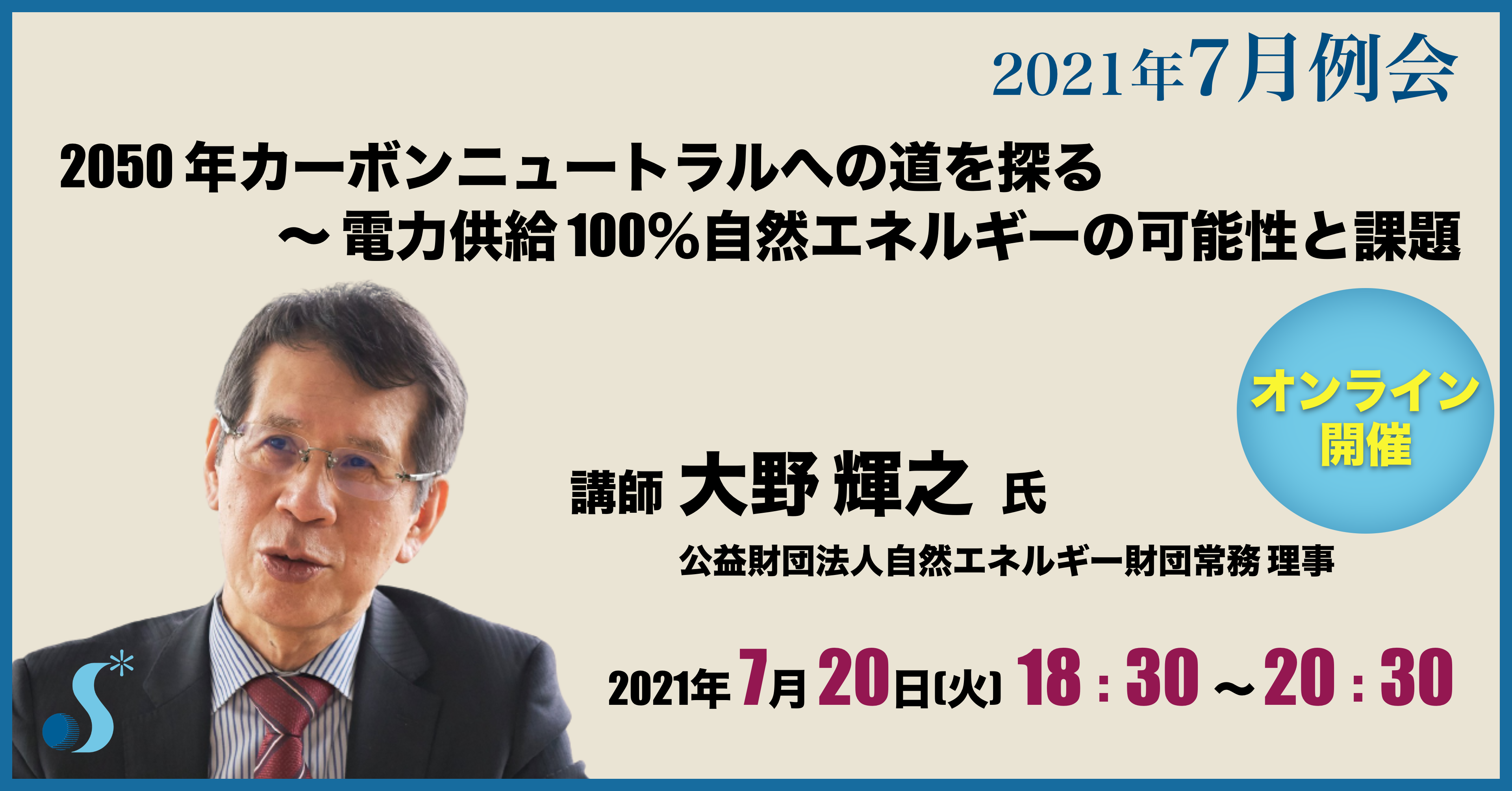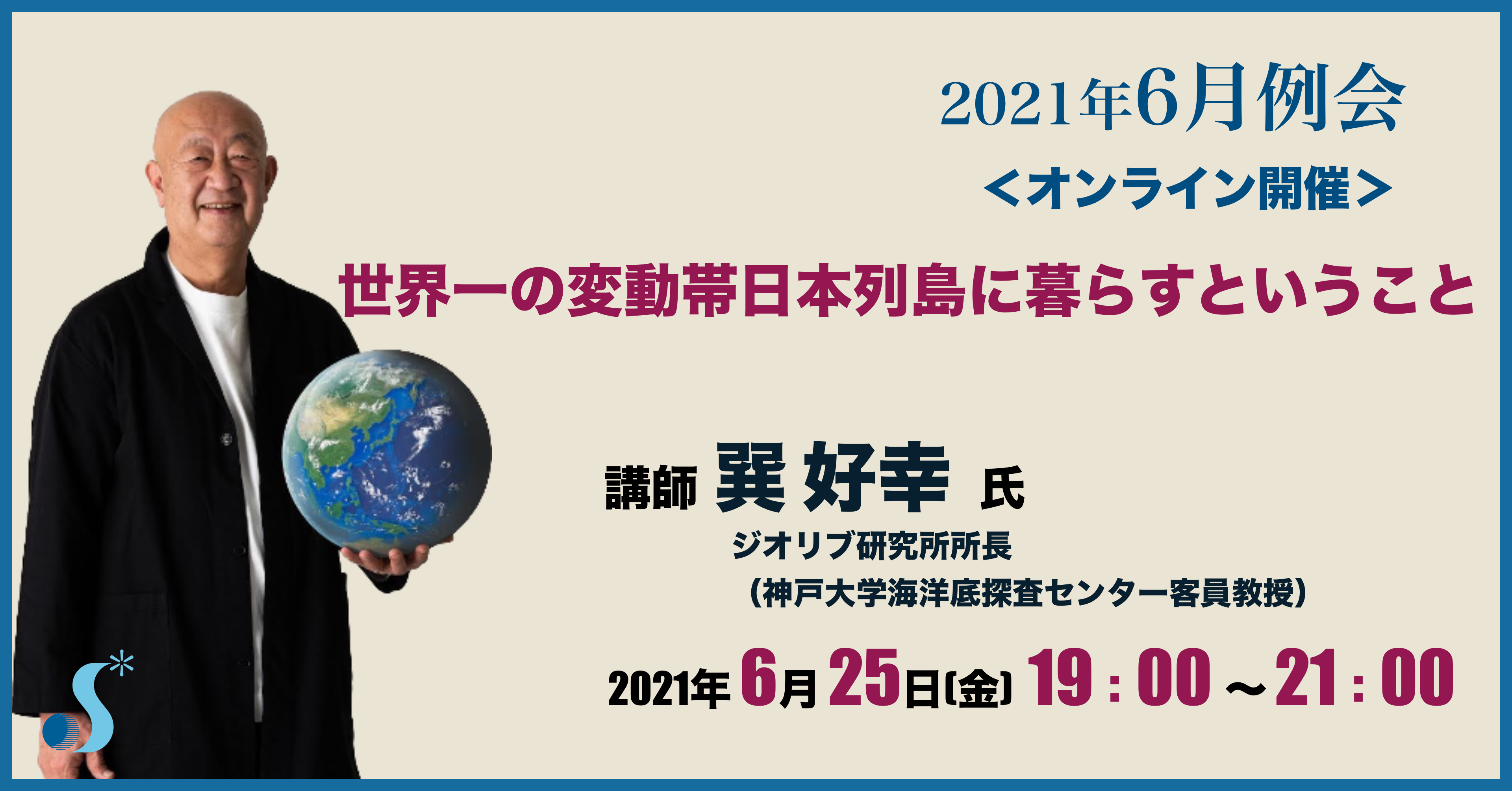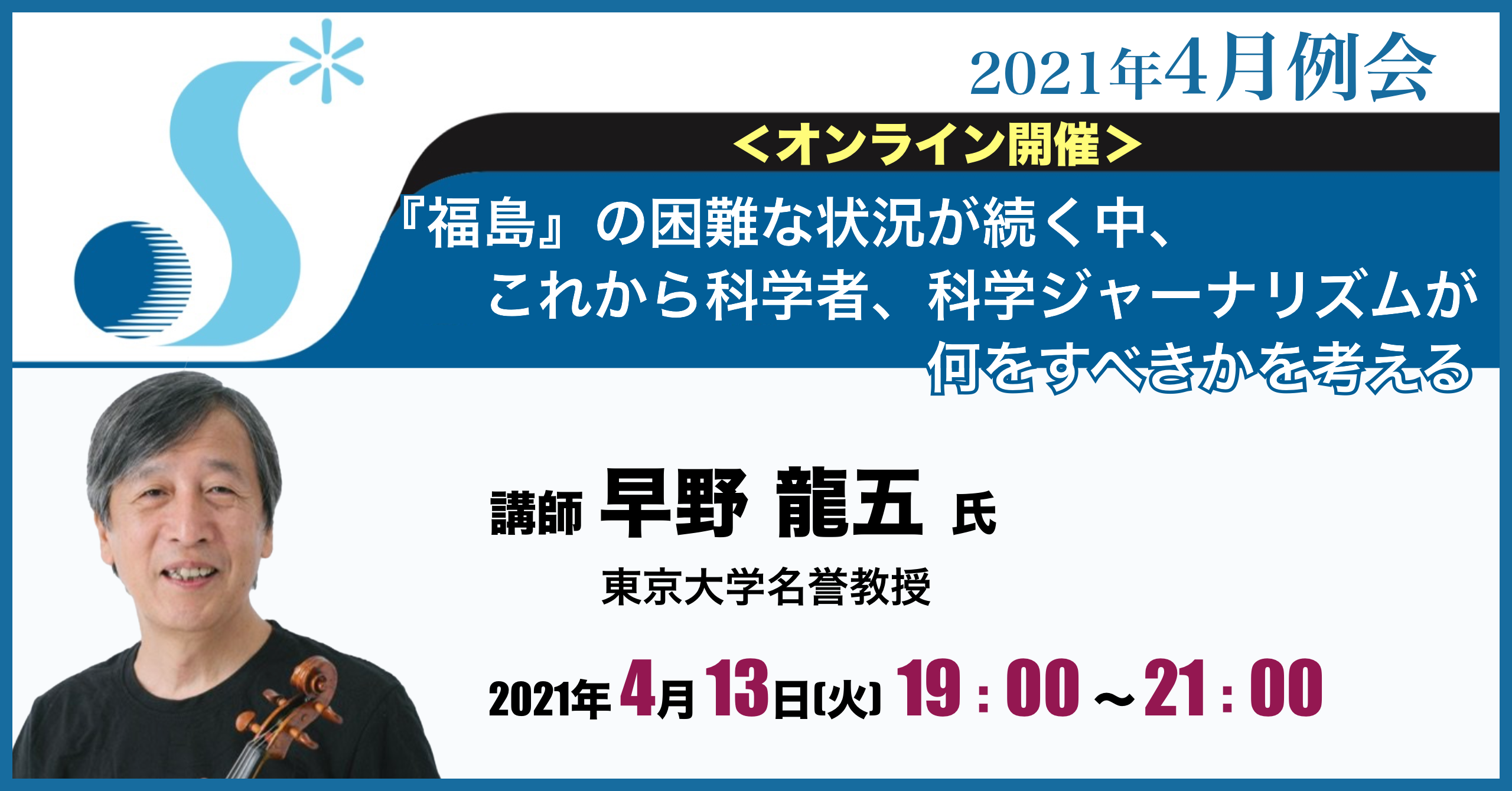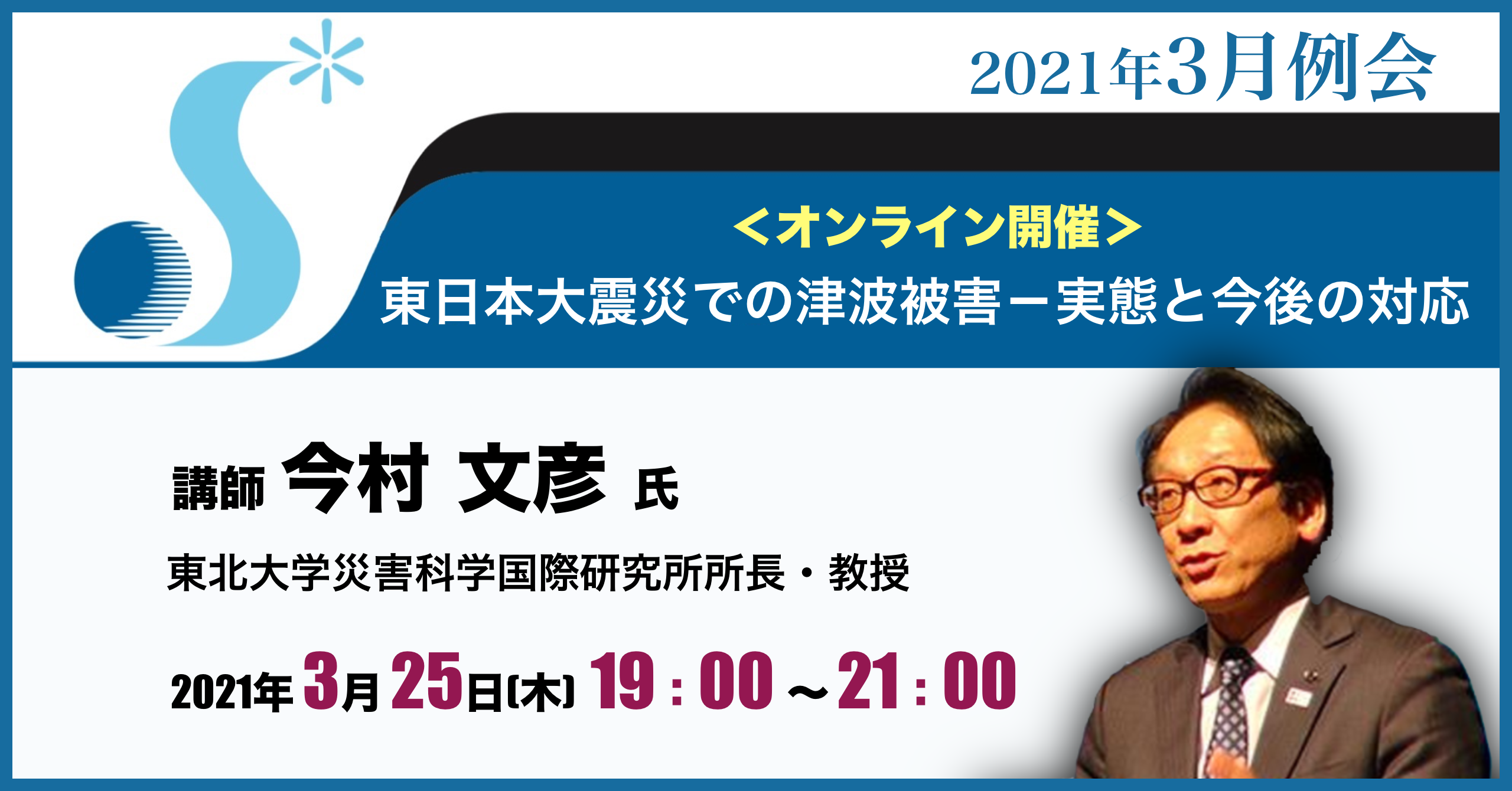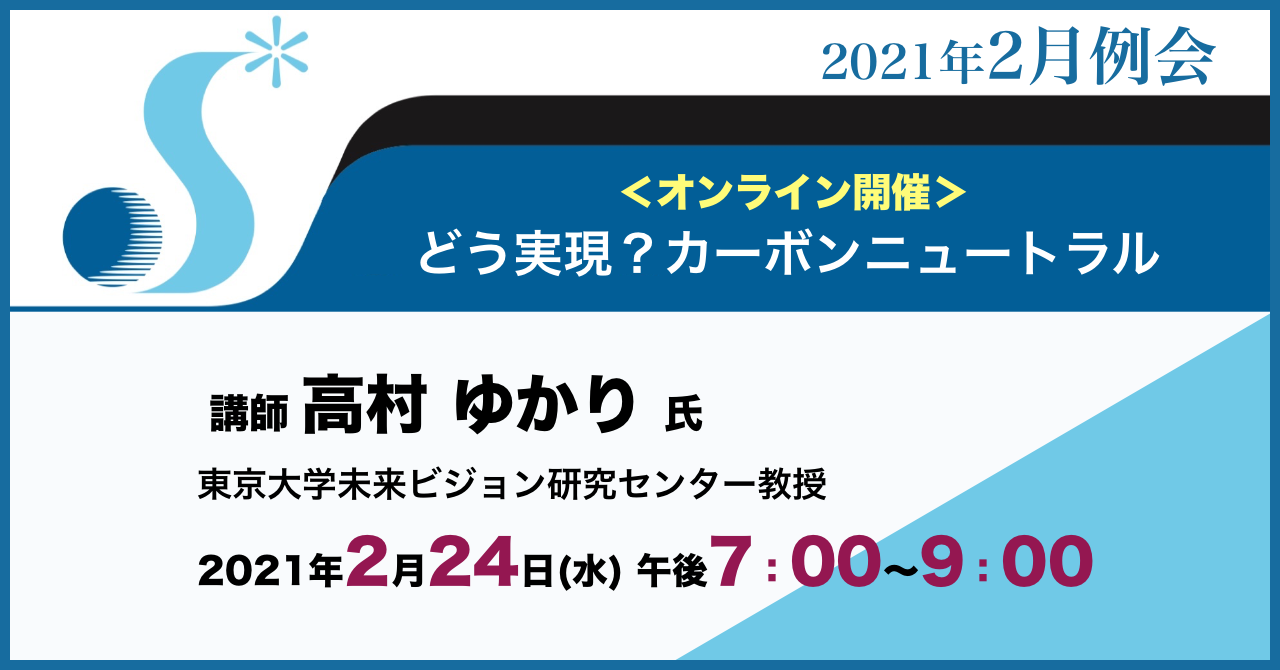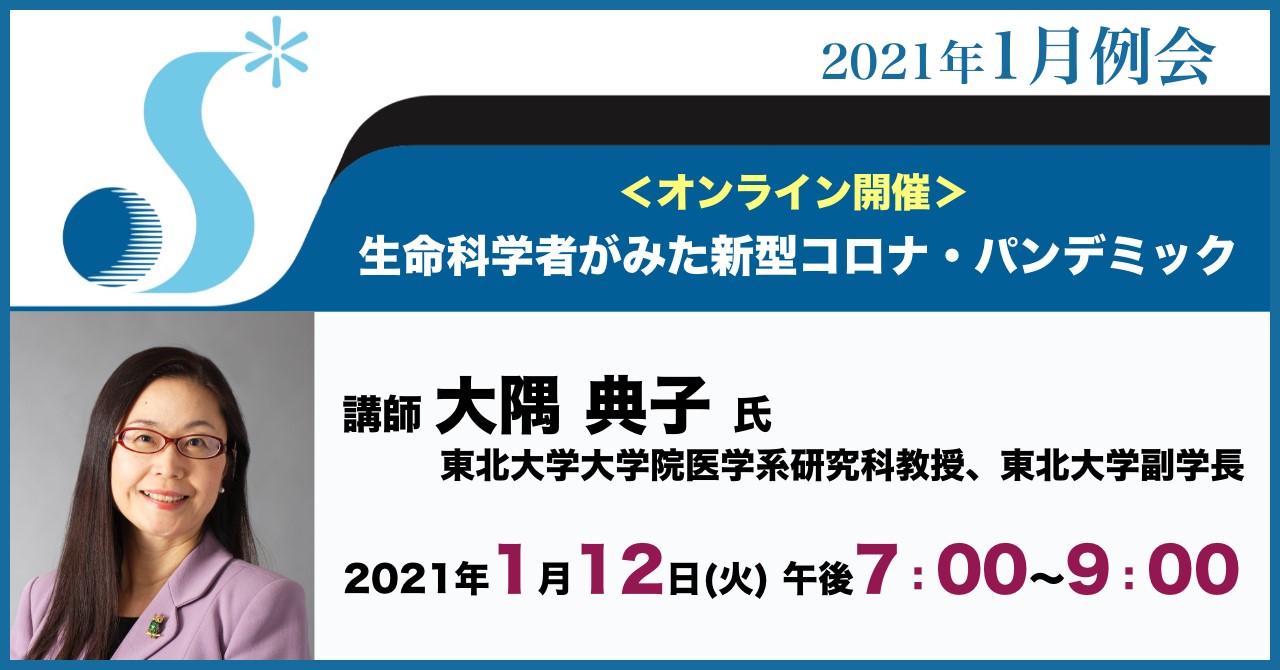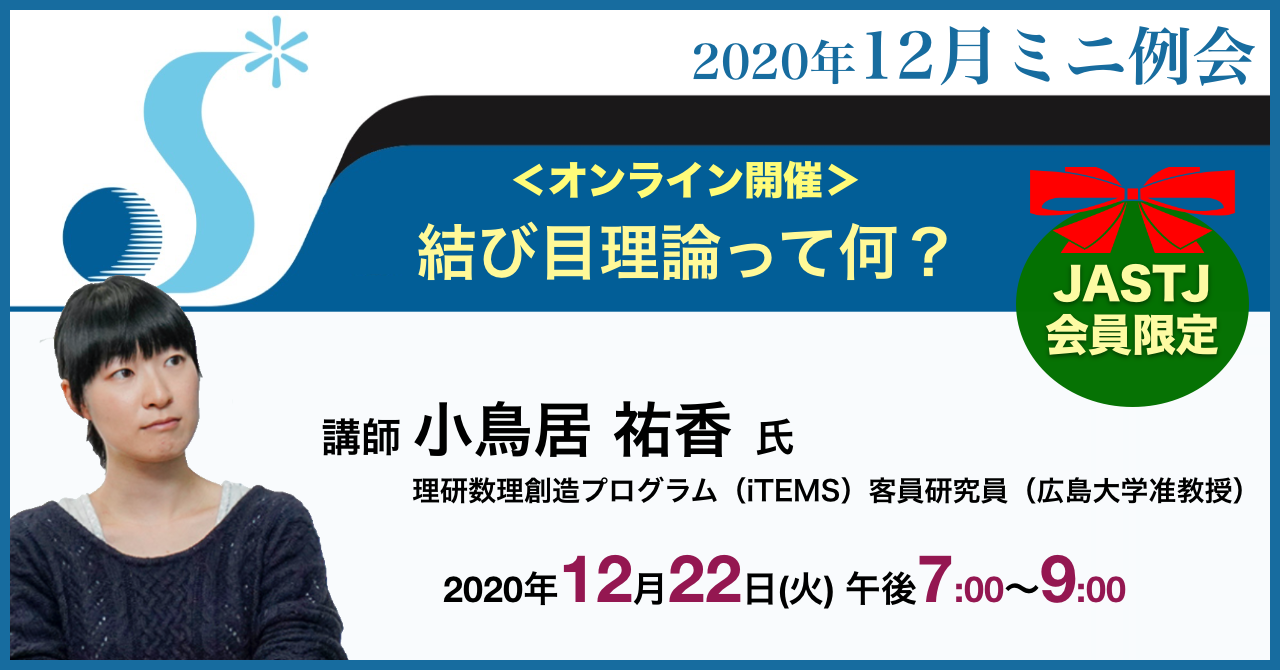日本科学技術ジャーナリスト会議(JASTJ、室山哲也会長)は4月16日、科学技術に関 する優れた報道や啓発活動などを顕彰する「科学ジャーナリスト賞」の選考委員会を開き、 2022年度の受賞作品を決定した。NHK メルトダウン取材班の書籍「福島第一原発事故 の『真実』」(講談社)を「科学ジャーナリスト大賞」に選定、そのほか3作品を「科学ジャ ーナリスト賞優秀賞」とした。大賞選出は19年度以来、3年ぶり。
22年度は新聞4作品、書籍40作品、映像25作品、ウェブ2作品、ラジオ1作品の合 計72作品の応募があり、この中からJASTJ 会員による一次選考で新聞1作品、書籍4作 品、映像4作品、ウェブ2作品を選び、最終選考会(メンバーは下記)で審査し決定した。 なお応募作の総数は21年度の74作品とほぼ同水準だった。
賞の贈呈式は6月4日に東京・内幸町の日本プレスセンタービル10階ホールで開催する予定である。
【科学ジャーナリスト大賞】 1 件
NHK メルトダウン取材班(代表・近堂靖洋)殿
書籍「福島第一原発事故の『真実』」
(講談社)
福島第1原発事故の原因や経過に関し、取材班が10年をかけて多数の関係者に取材し膨大な資料を集めて検証した。記録性と資料としての価値も高く評価した。
【科学ジャーナリスト賞(優秀賞)】 3 件(順不同)
下野新聞 健康と社会的処方取材班(代表・大塚順一)殿
新聞連載「なぜ君は病に…社会的処方 医師たちの挑戦」
(2019年11月26日〜2021年6月7 日連載)
地域の医師が患者の社会や家庭環境に着目し患者に向き合う「社会的処方」に取り組む姿をルポし、病の本質に潜む要因を掘り起こした点が評価された。
サイエンス作家 中嶋彰殿
書籍「早すぎた男 南部陽一郎物語 時代は彼に追いついたか」
(講談社ブルーバックス)
一般に広く読まれる評伝がなかった南部氏について、生い立ちや人柄、交友関係まで関係者の話を丹念に聞き、「早すぎた大科学者」の生涯とその研究成果に迫った数少ない記 録として評価した。
北海道放送報道部デスク 山﨑裕侍(やまざきゆうじ)殿
映像「ネアンデルタール人は核の夢を見るか〜“核のごみ”と科学と民主主義」
(2021年11月20日放送)
高レベル放射性廃棄物の最終処分場誘致に名乗りをあげた北海道寿都町の葛藤が地元テレビ局にしかできない現場密着のドキュメンタリーとして描かれた点を評価した。
<科学ジャーナリスト賞選考委員(50 音順、敬称略)>
〔有識者委員〕相澤益男(科学技術国際交流センター会長)、浅島誠(東京大学名誉教授)、 大隅典子(東北大学副学長、教授)、白川英樹(筑波大学名誉教授)、村上陽一郎(東京大学 名誉教授)
〔JASTJ委員〕 大池淳一(JASTJ 理事)、佐々義子(同)、三井誠(同)、元村有希子(同、 選考委員長)
<本件のお問い合わせ先>
日本科学技術ジャーナリスト会議(JASTJ)
〒100-0011 東京都千代田区内幸町 2-2-1 日本プレスセンタービル 8 階 848
メール awards@jastj.jp
担当理事 滝順一:090-5321-0309 事務局 中野薫:090-9370-4964