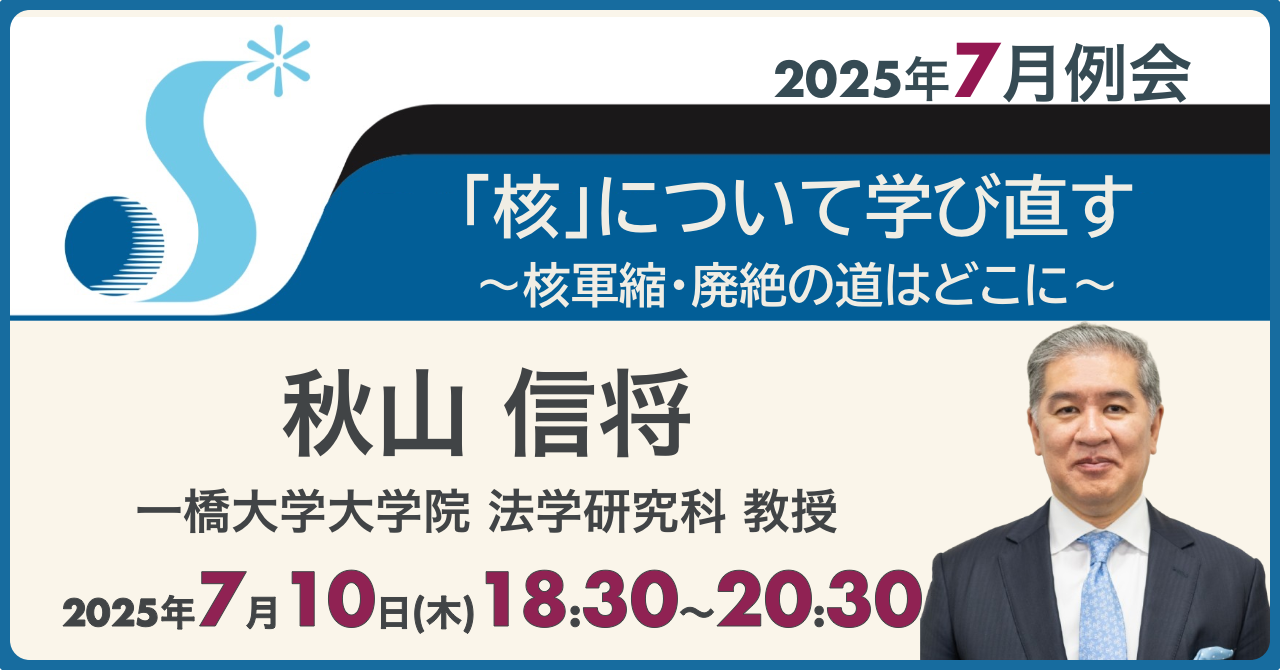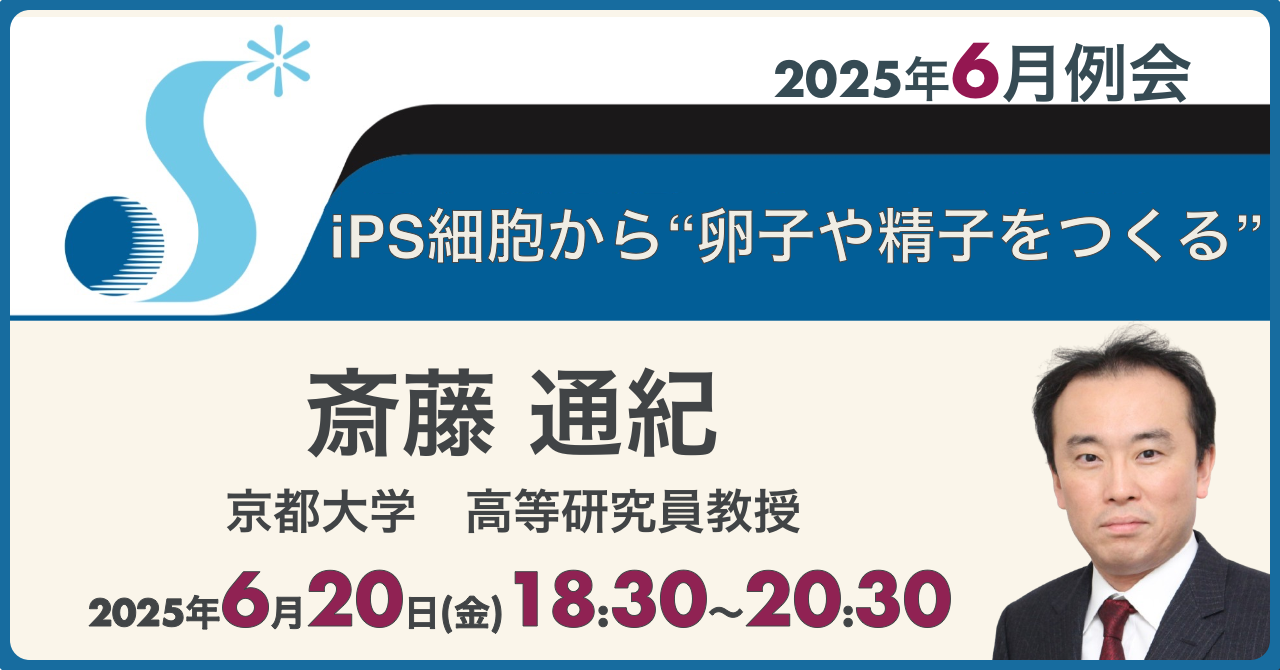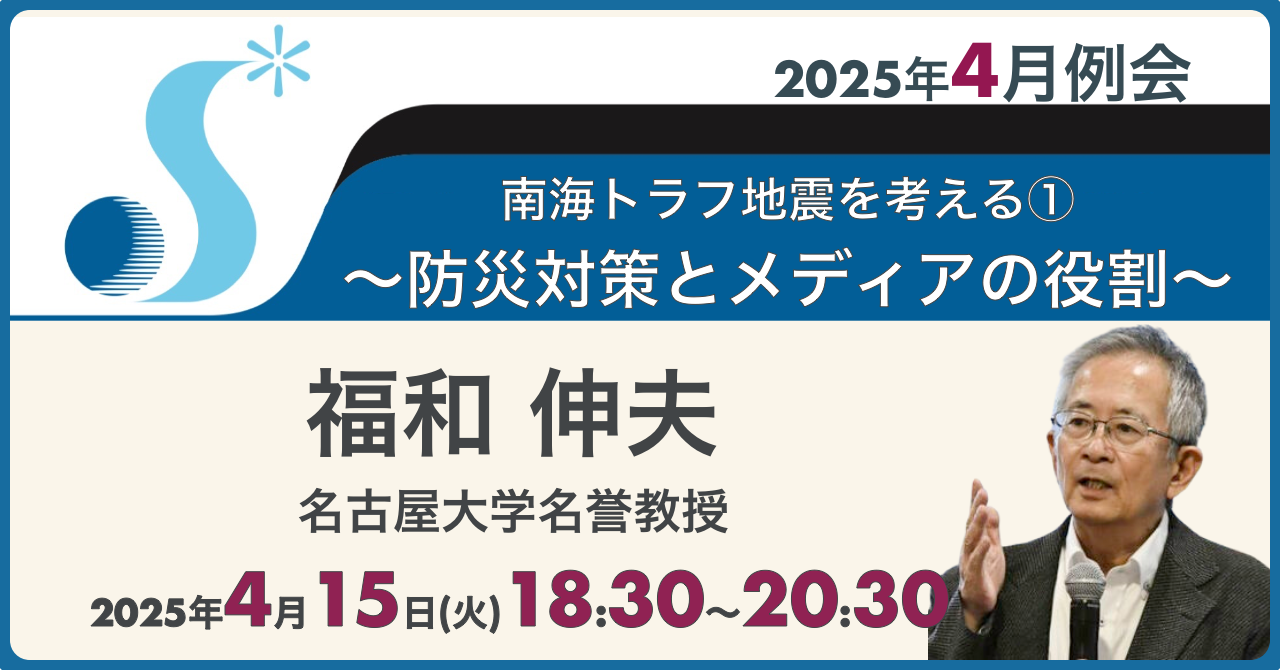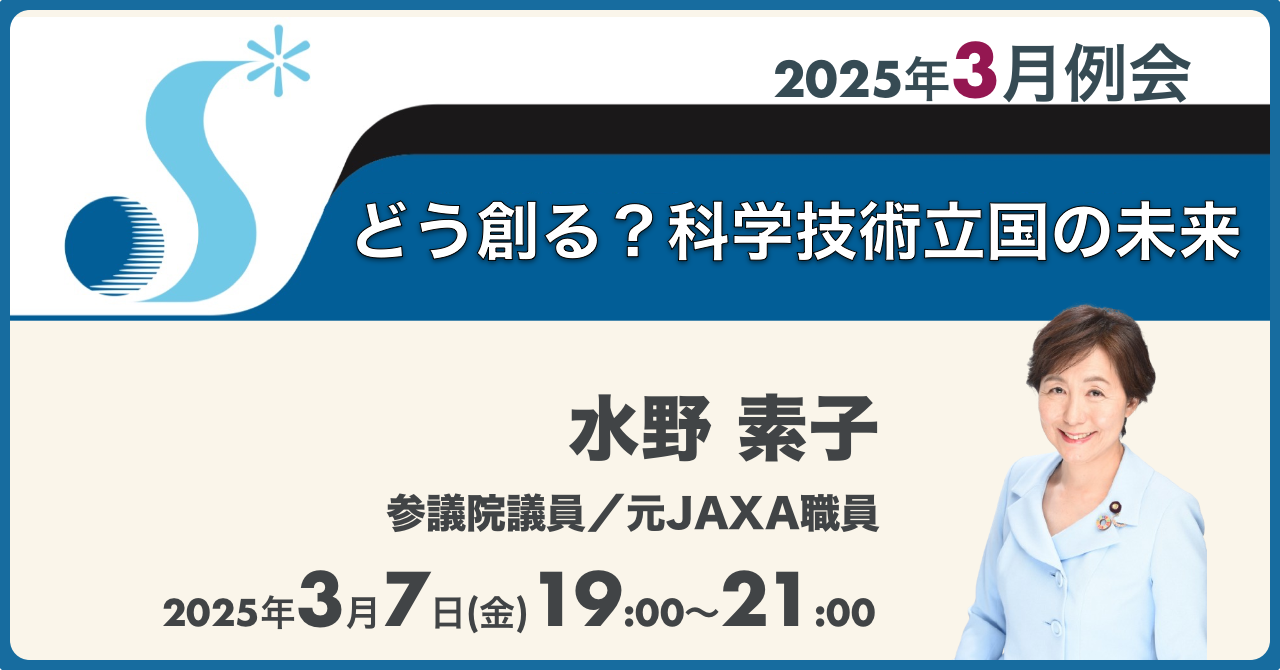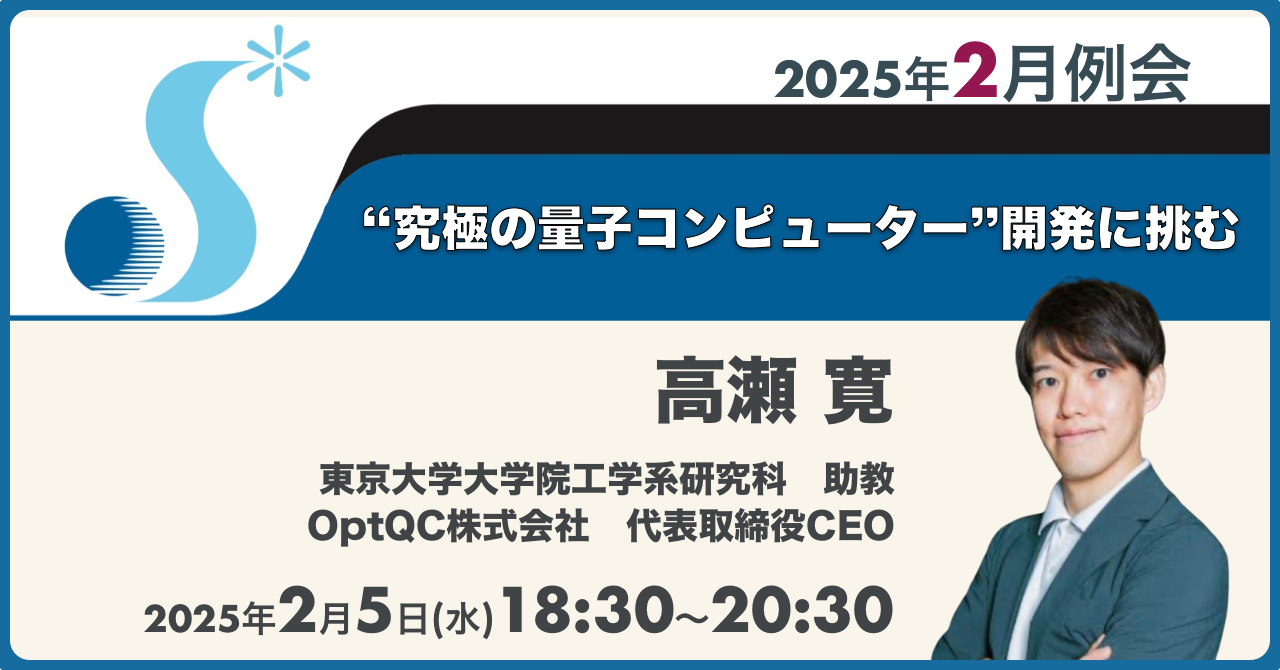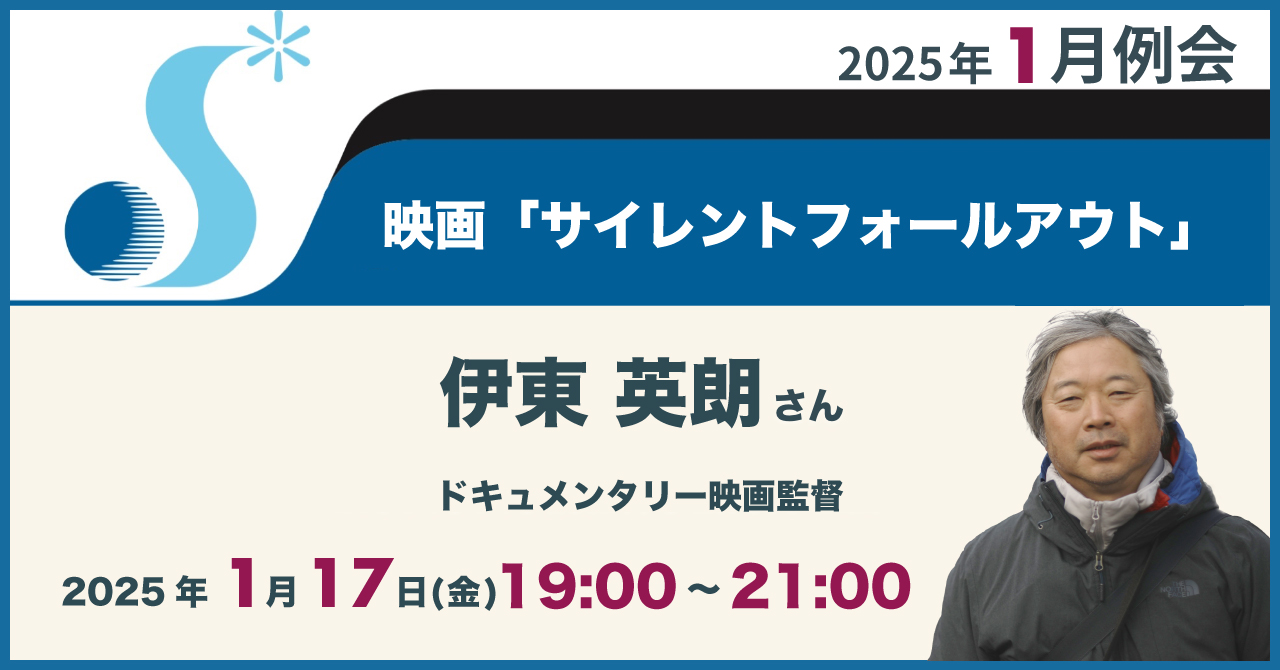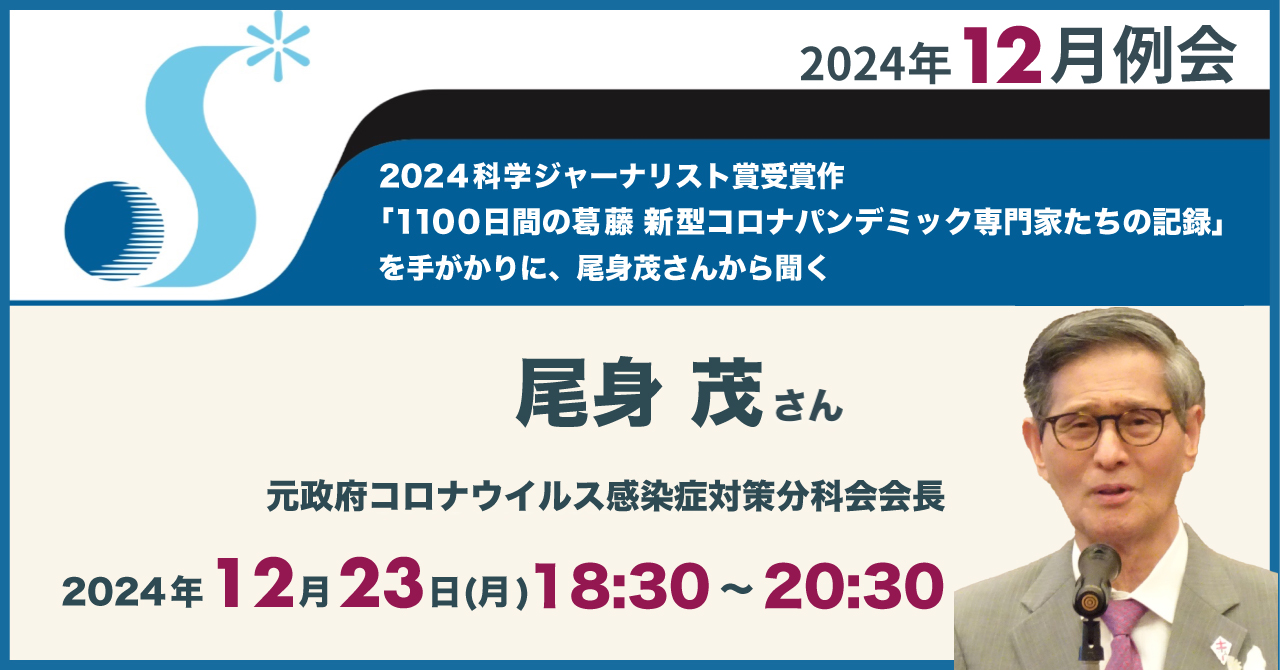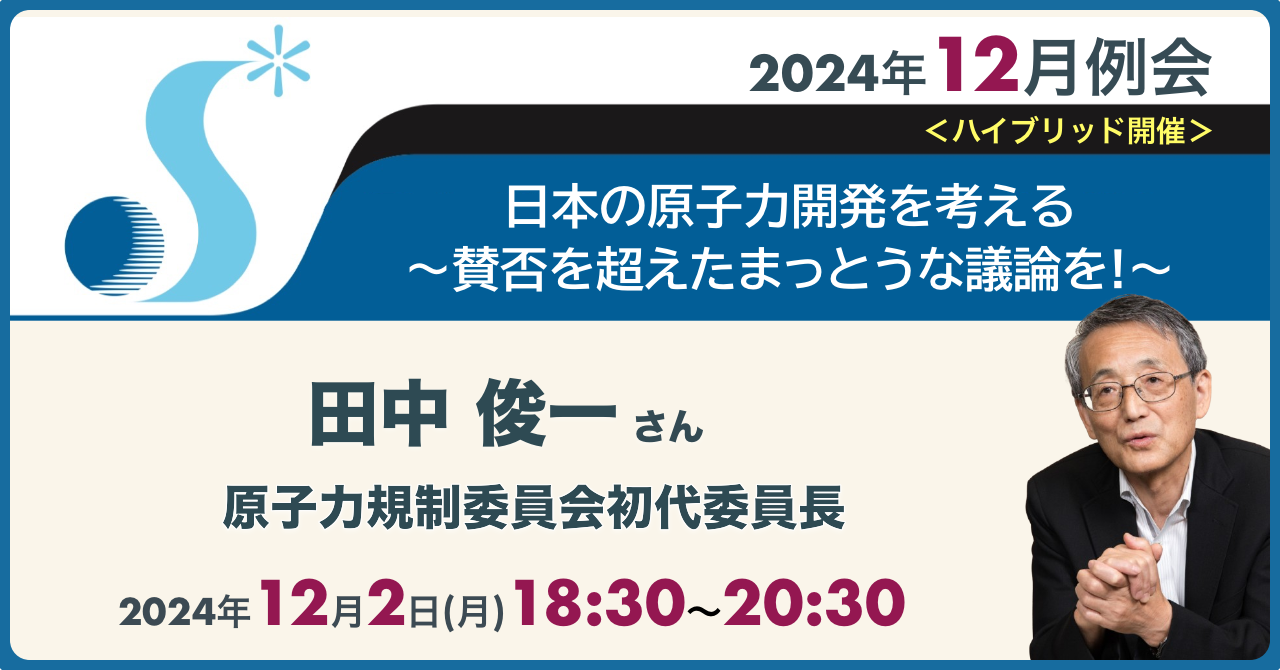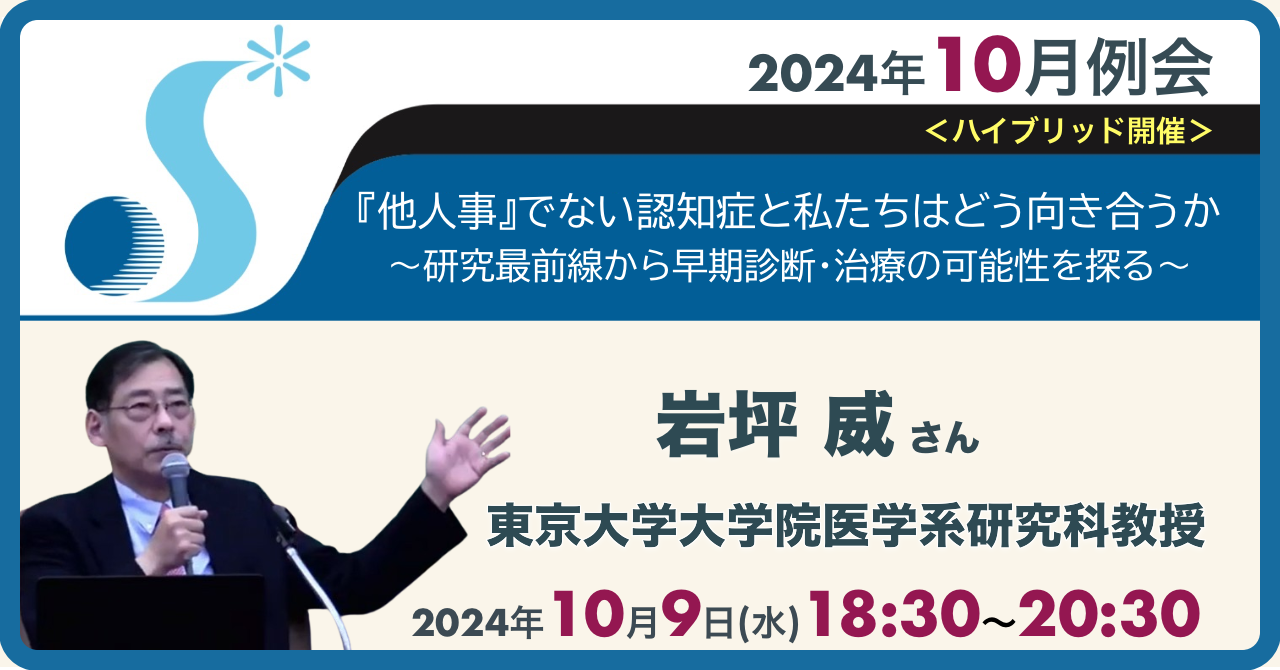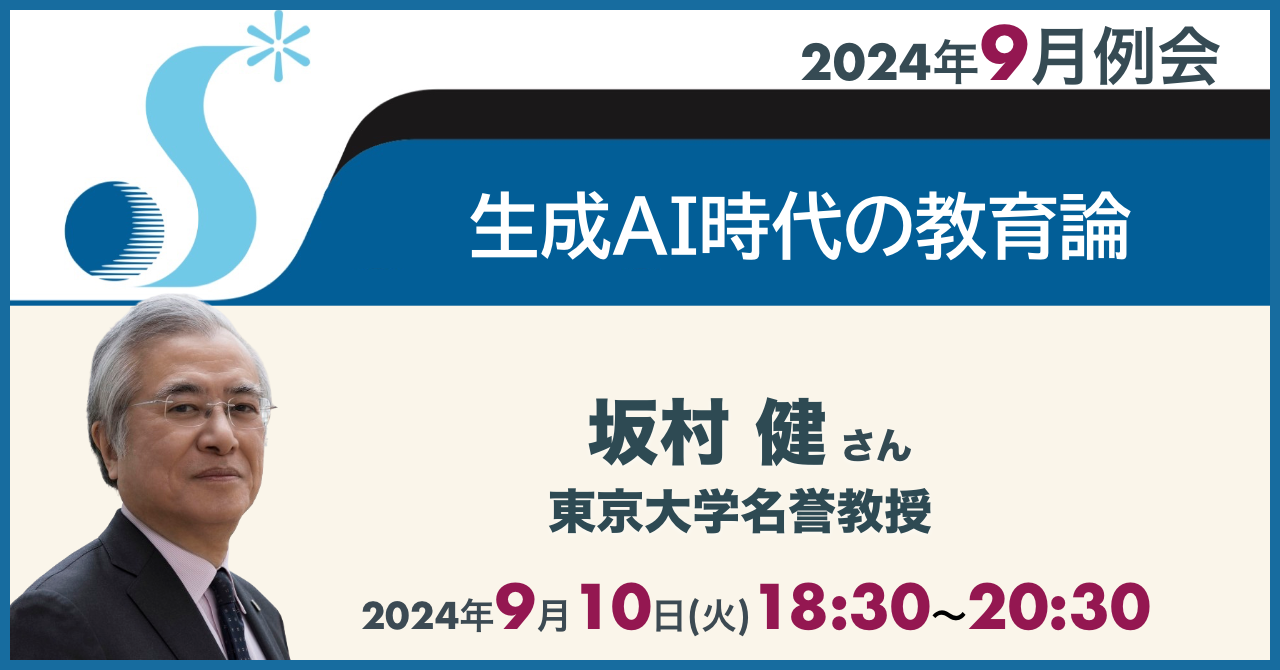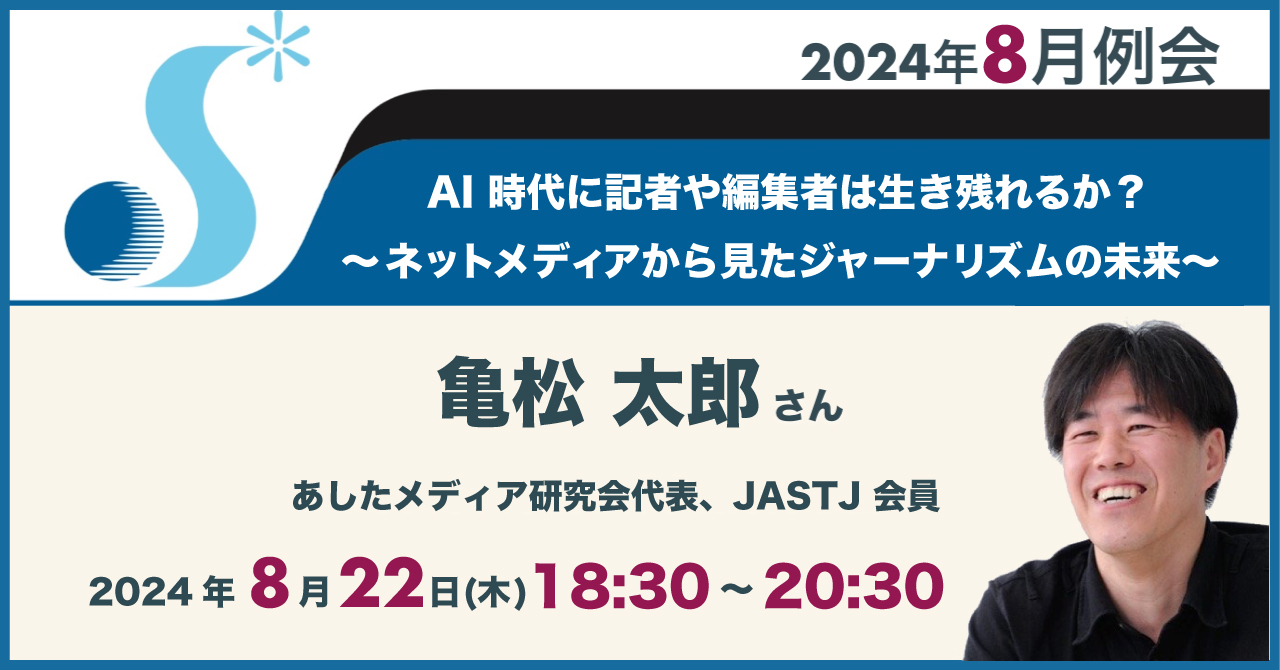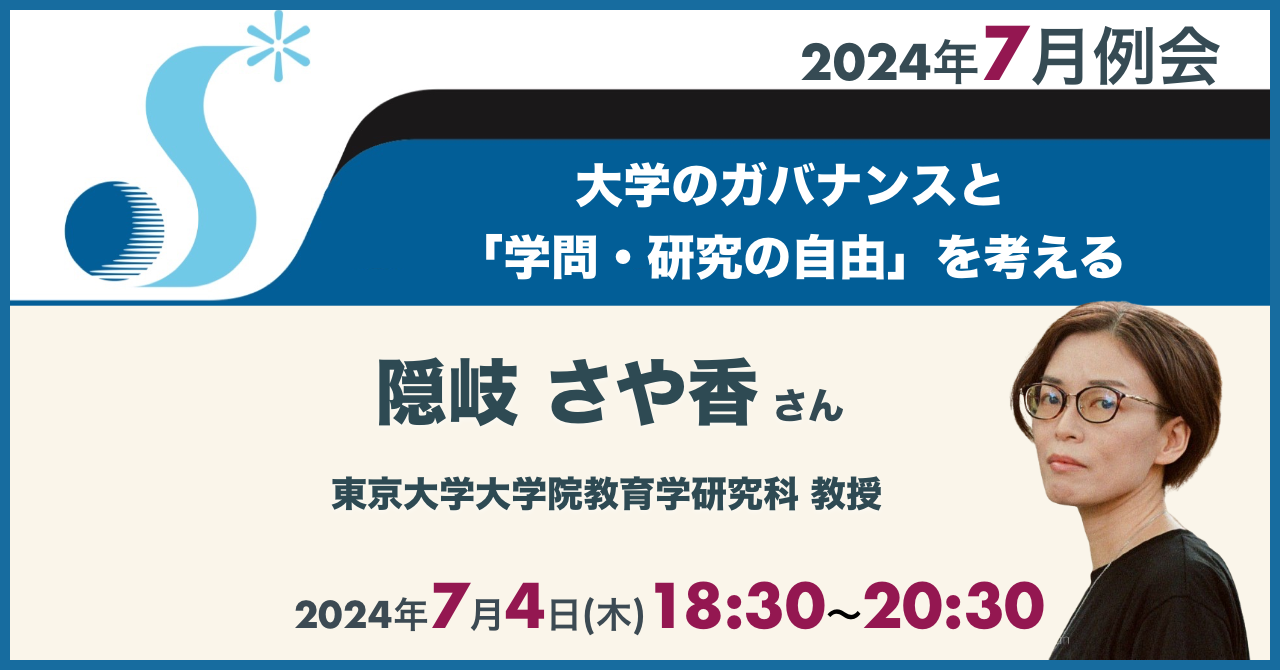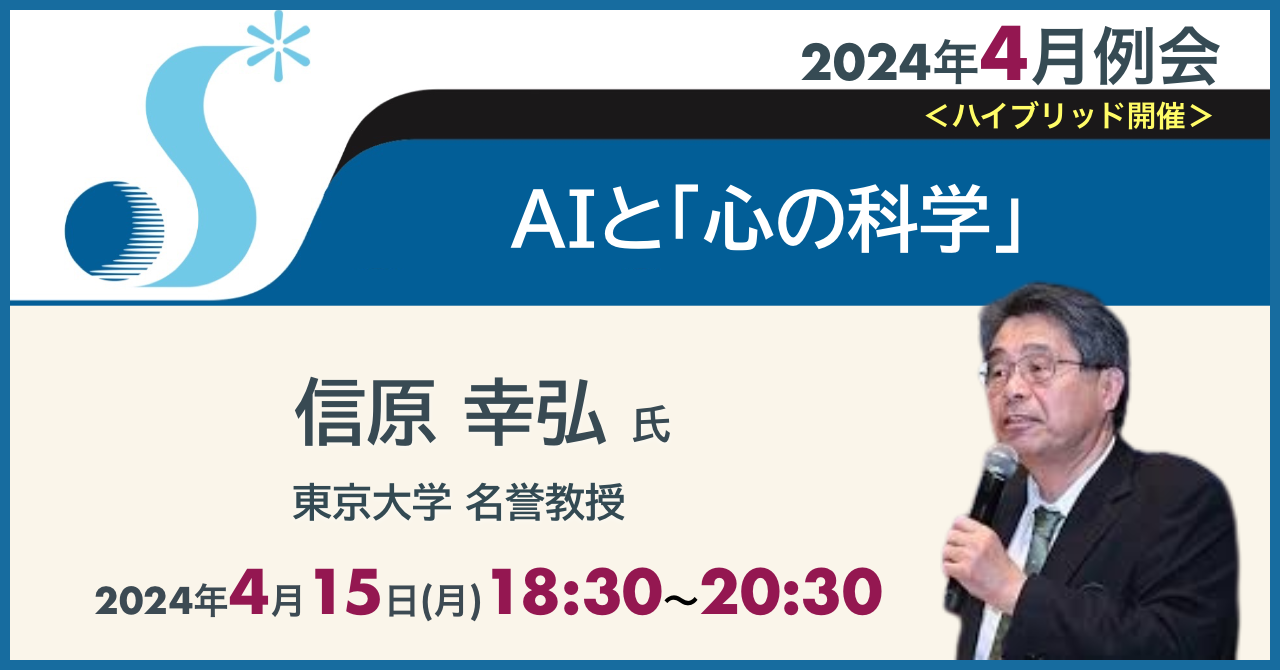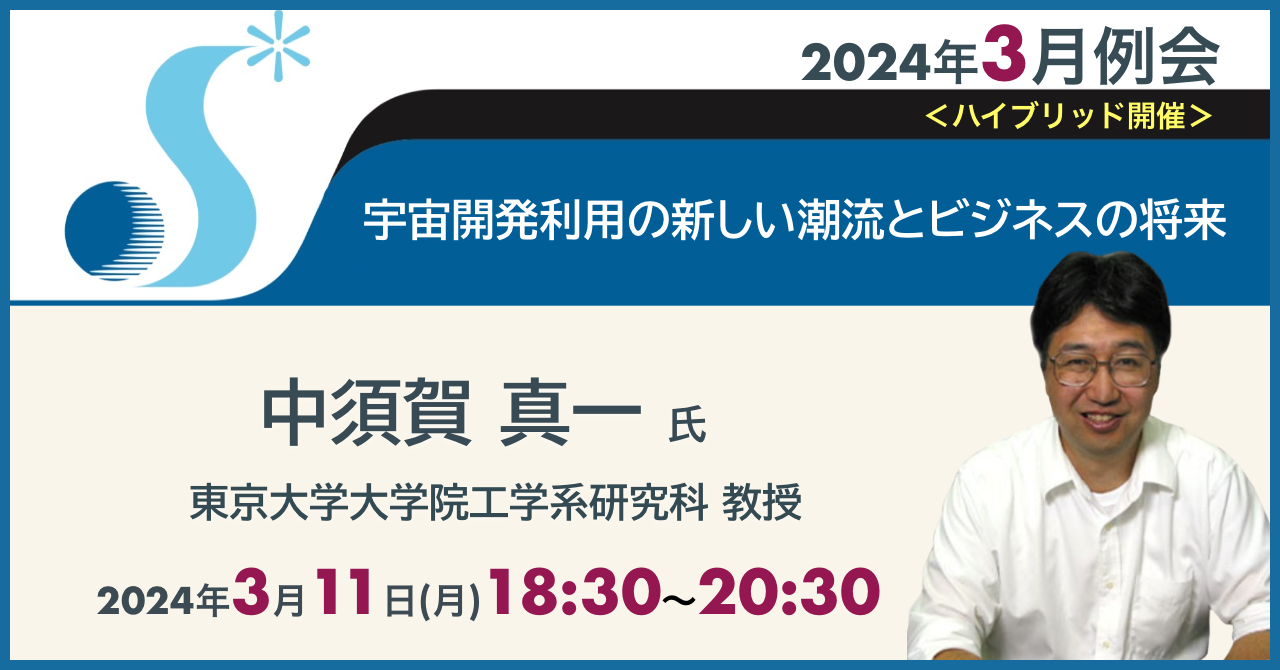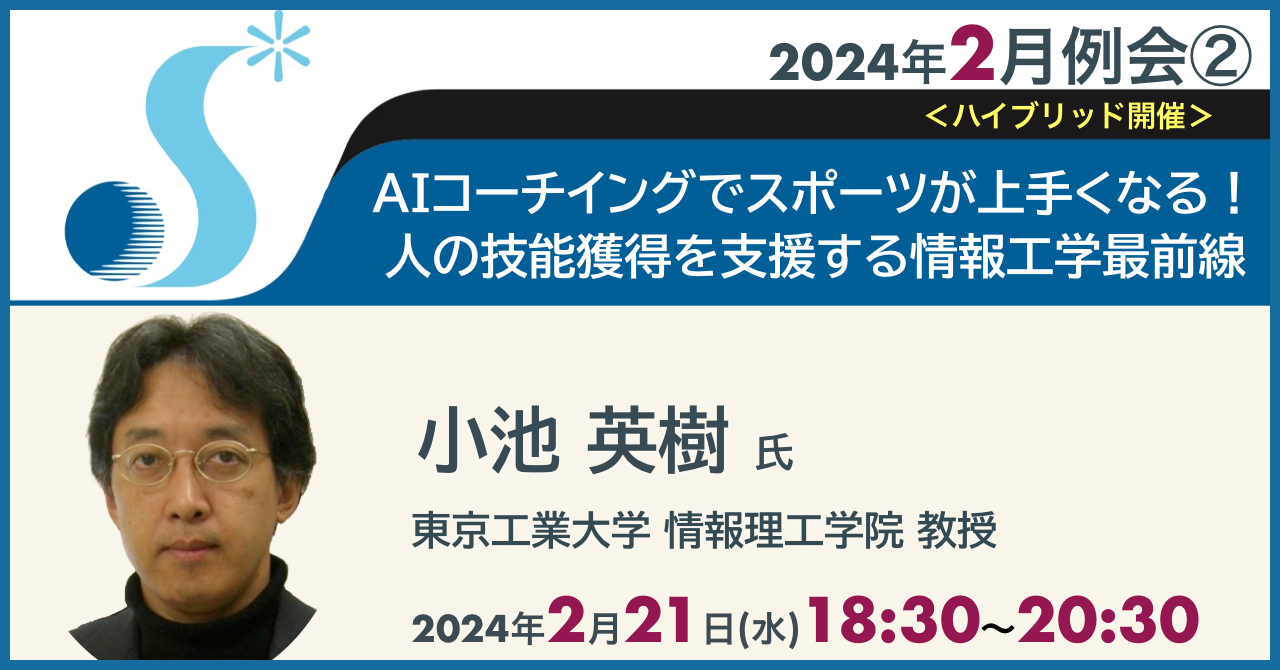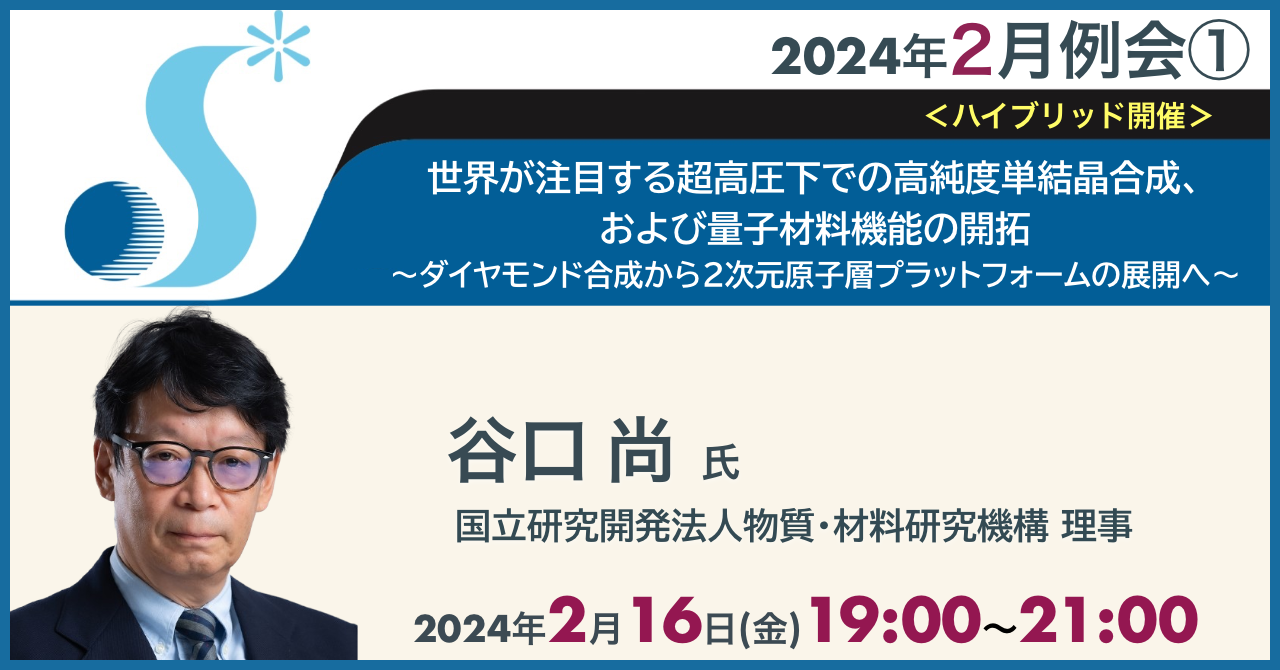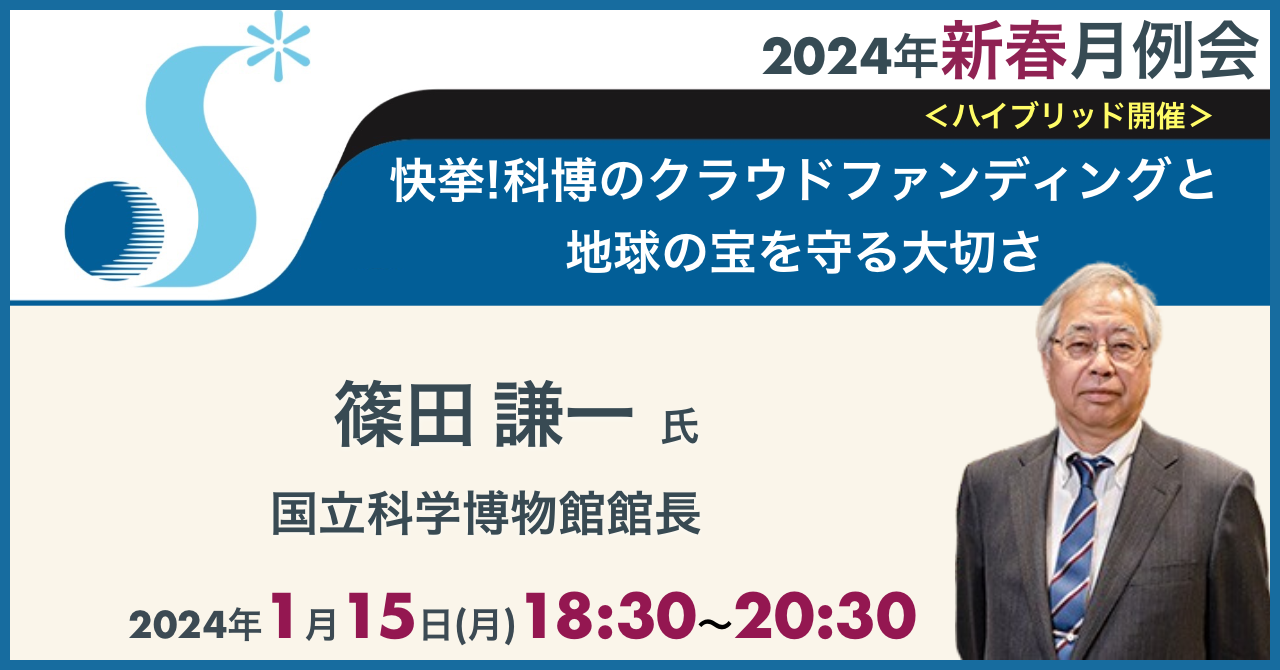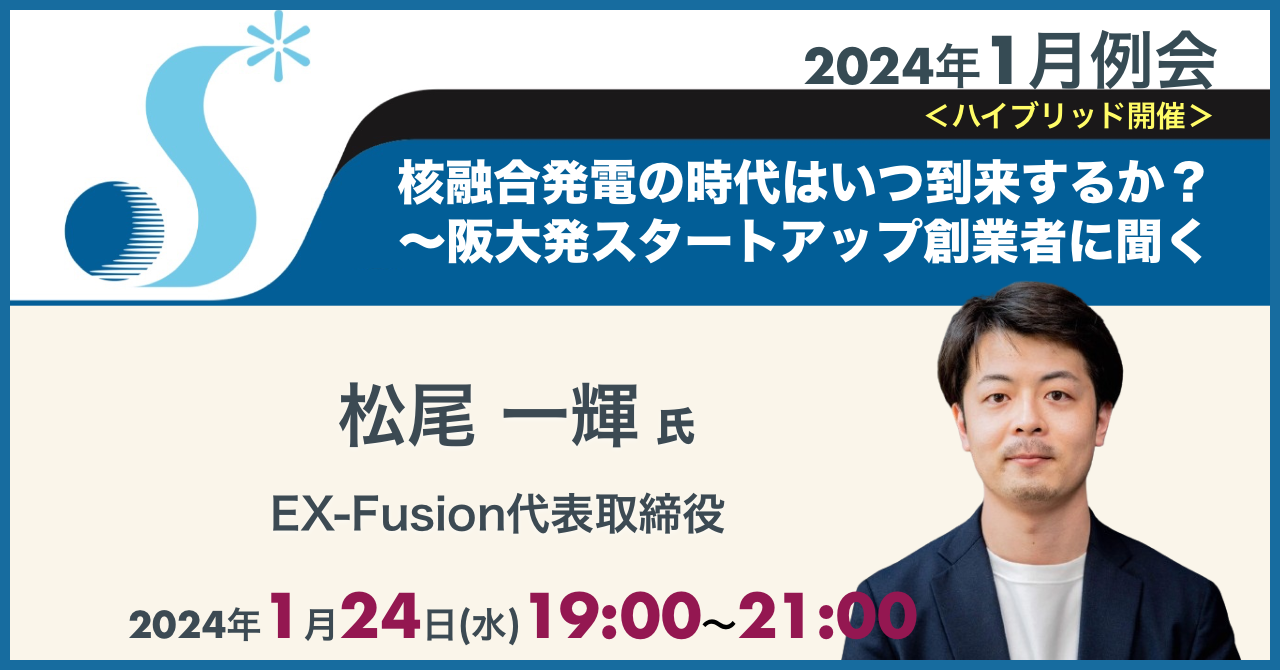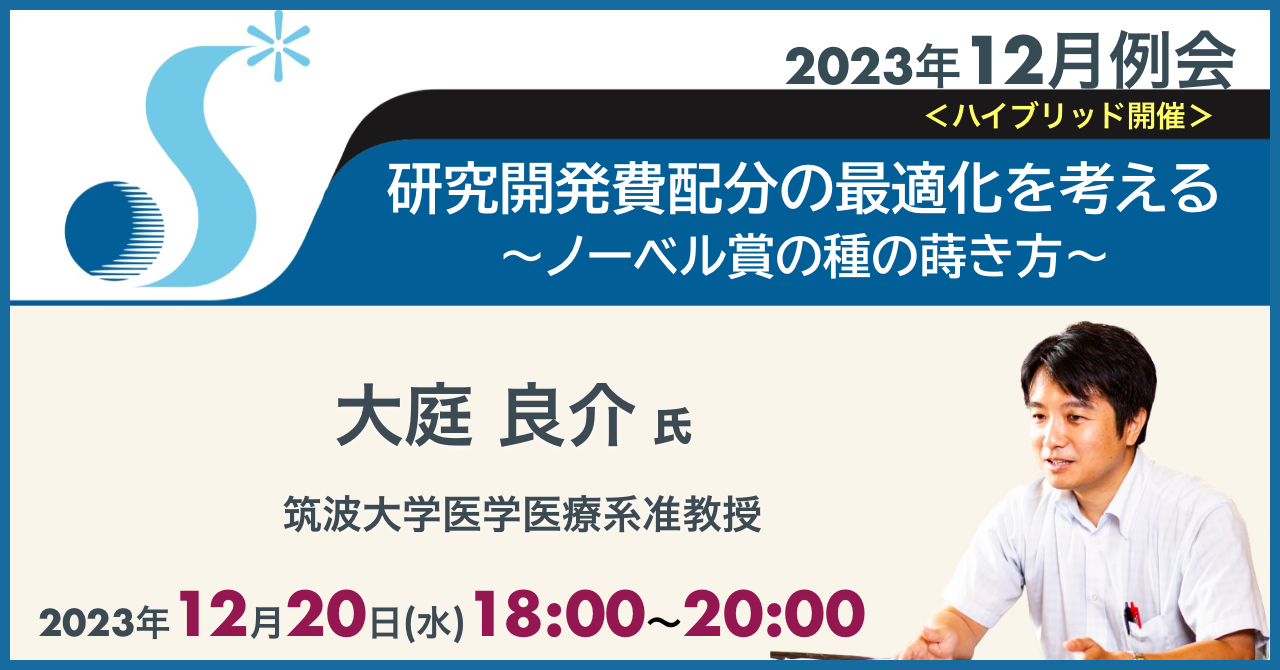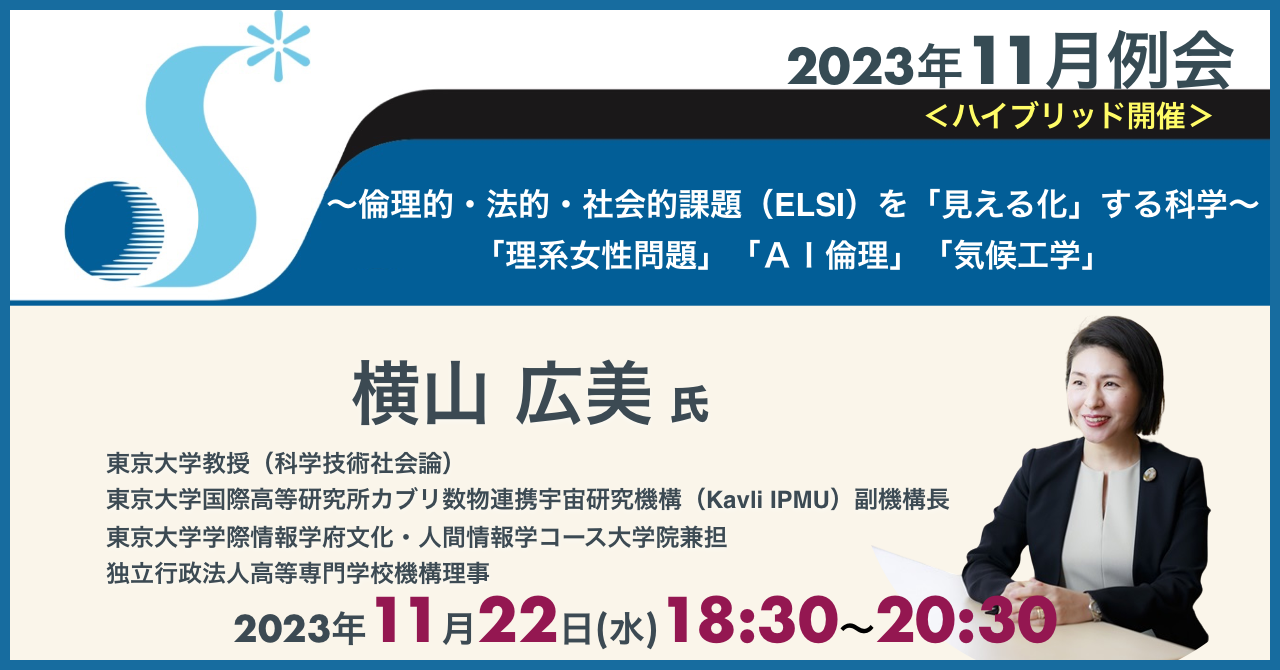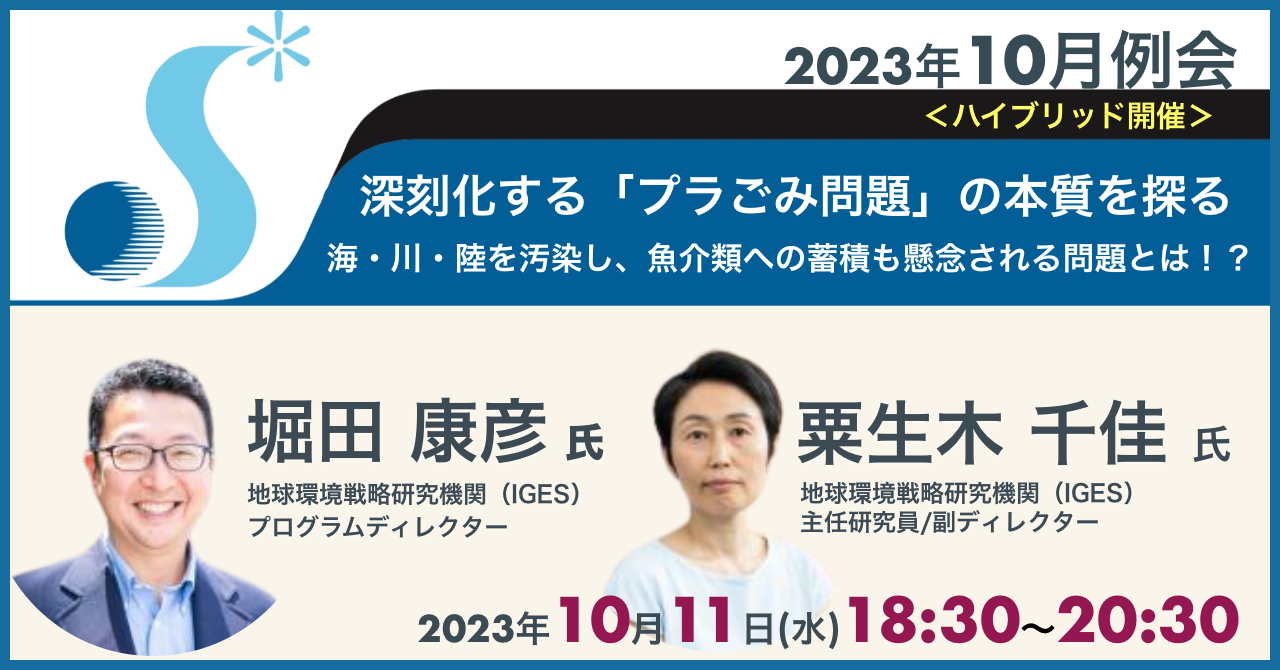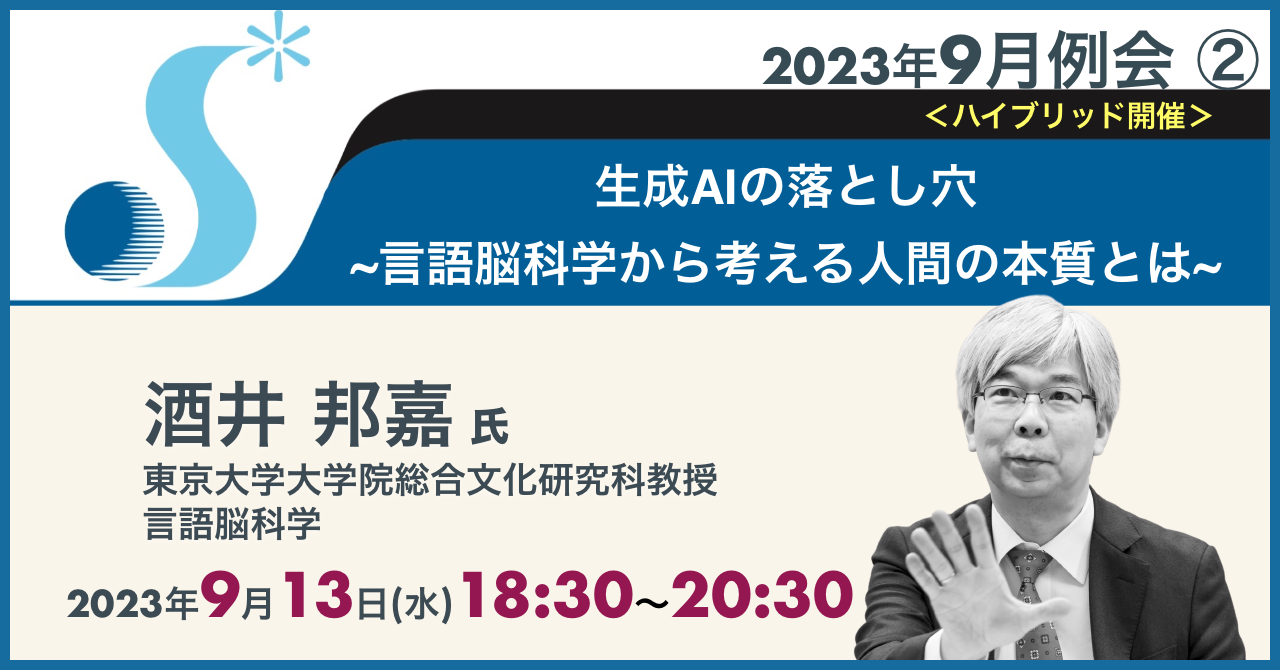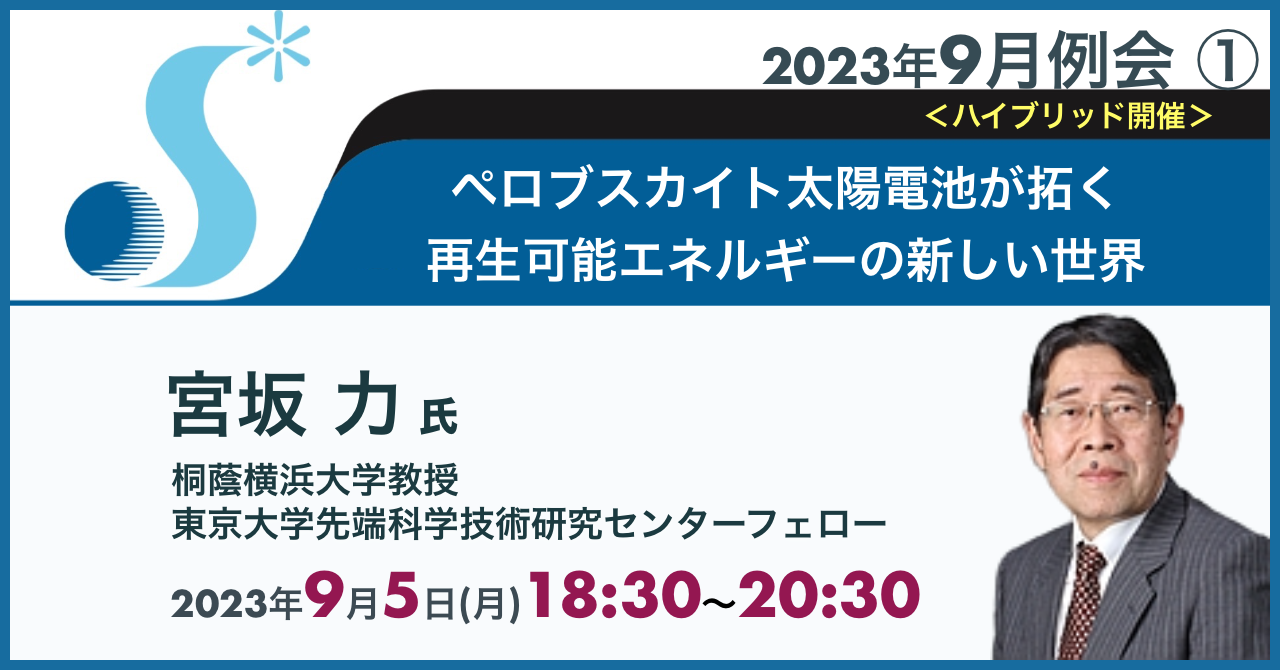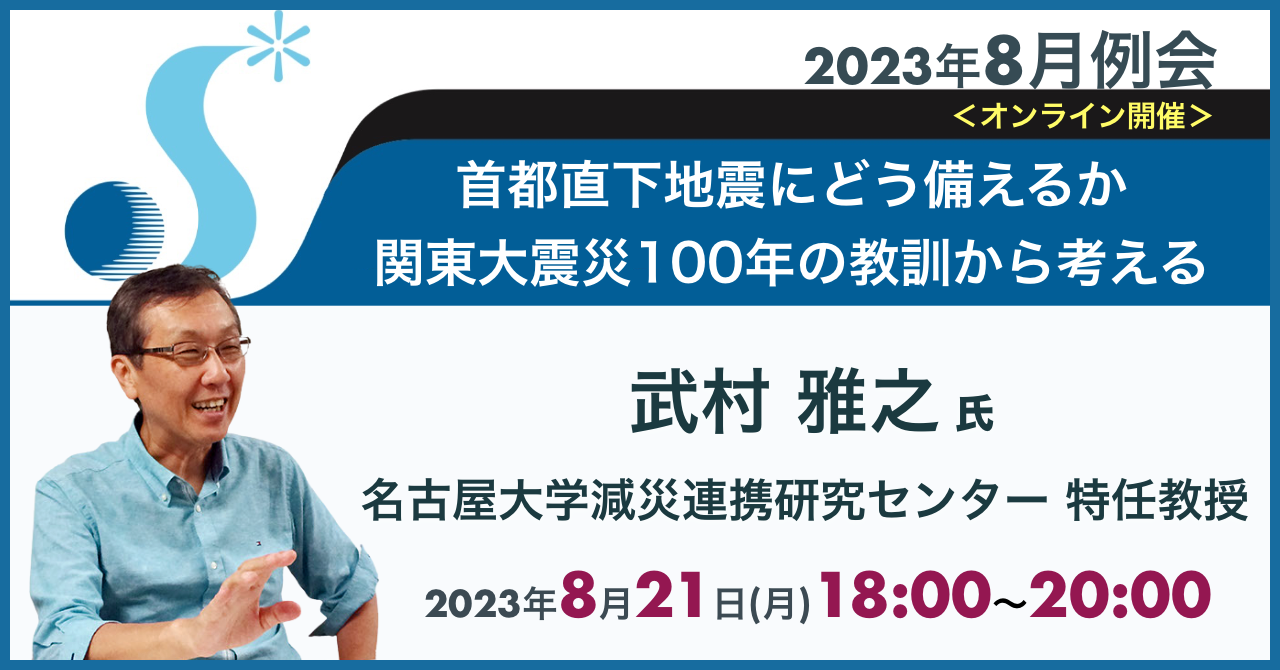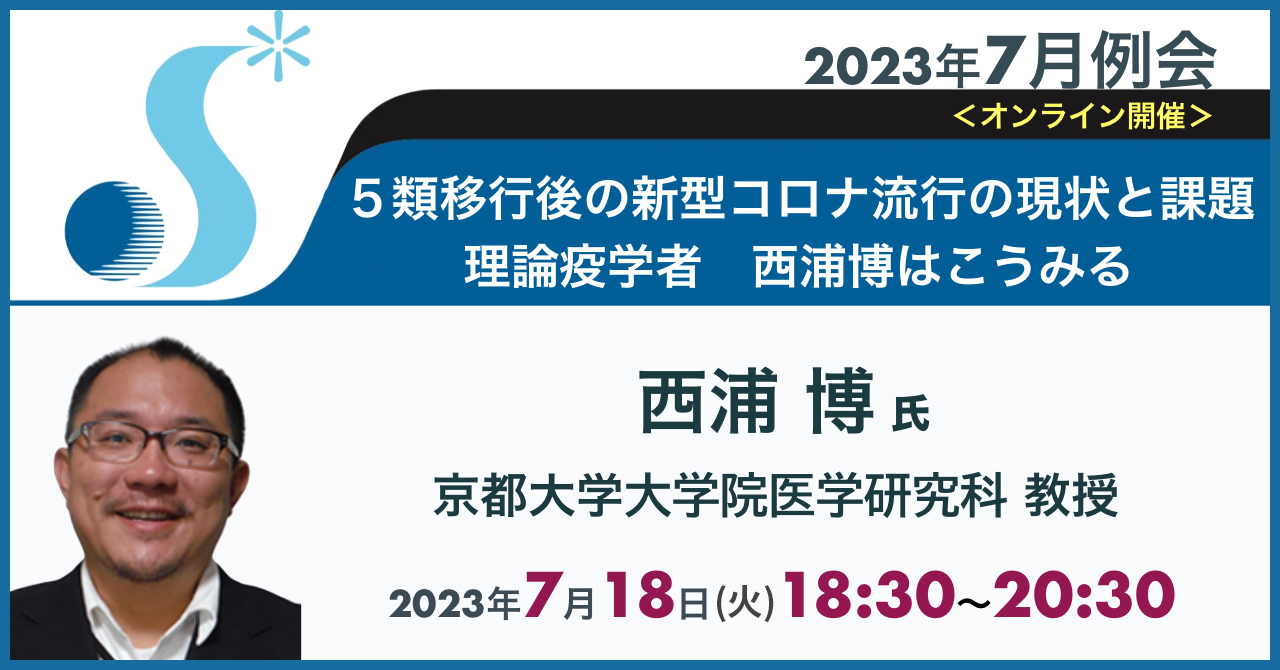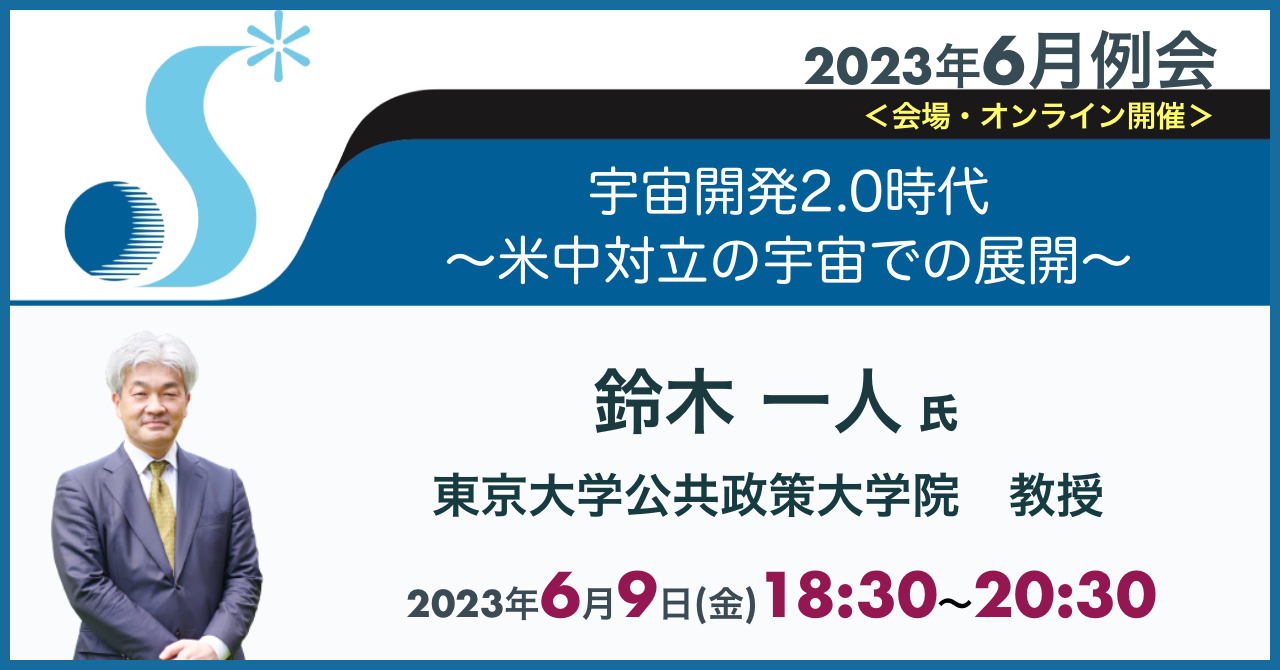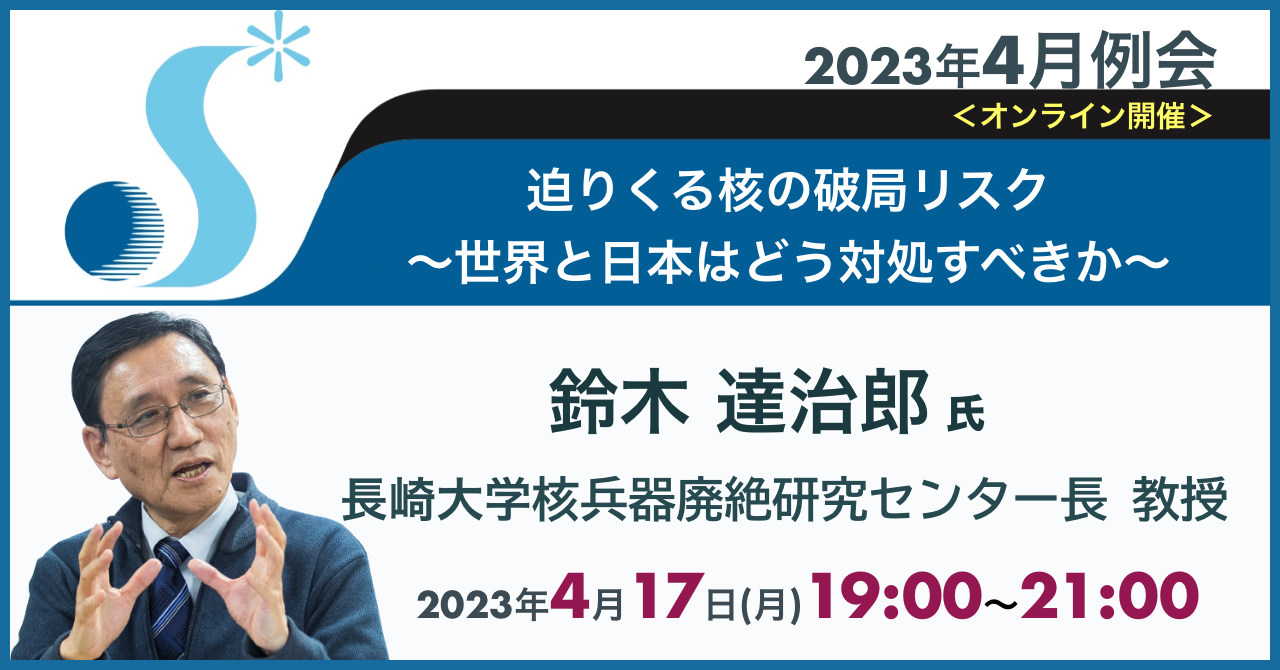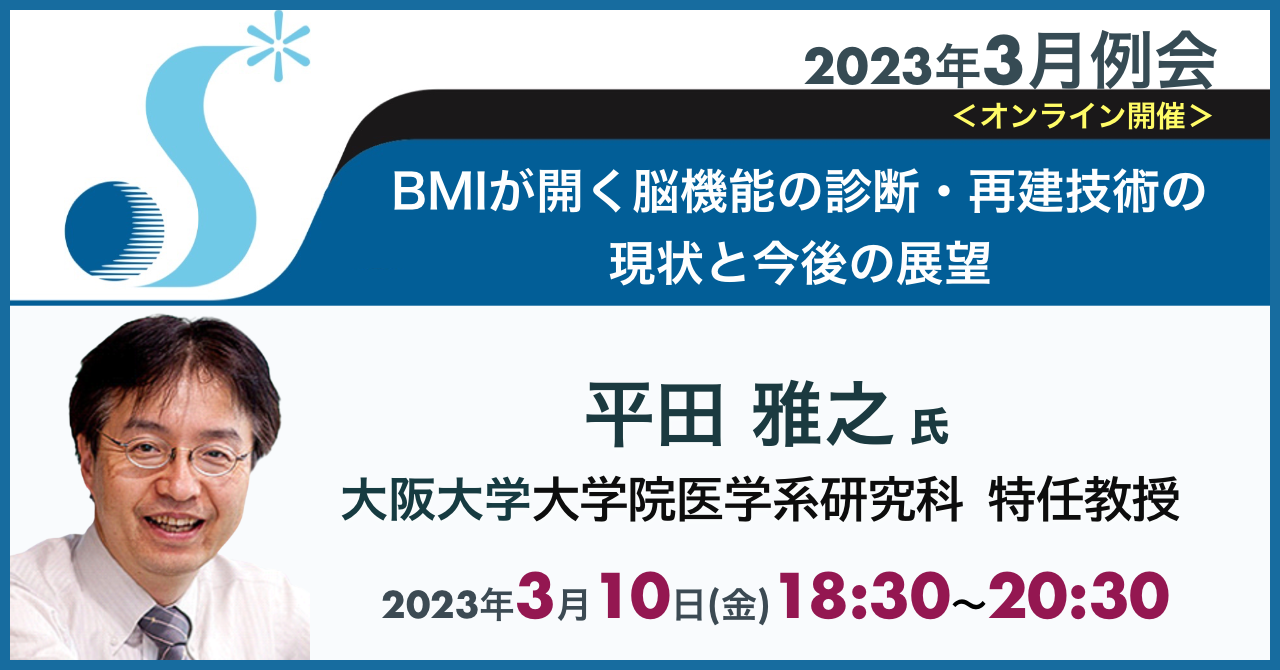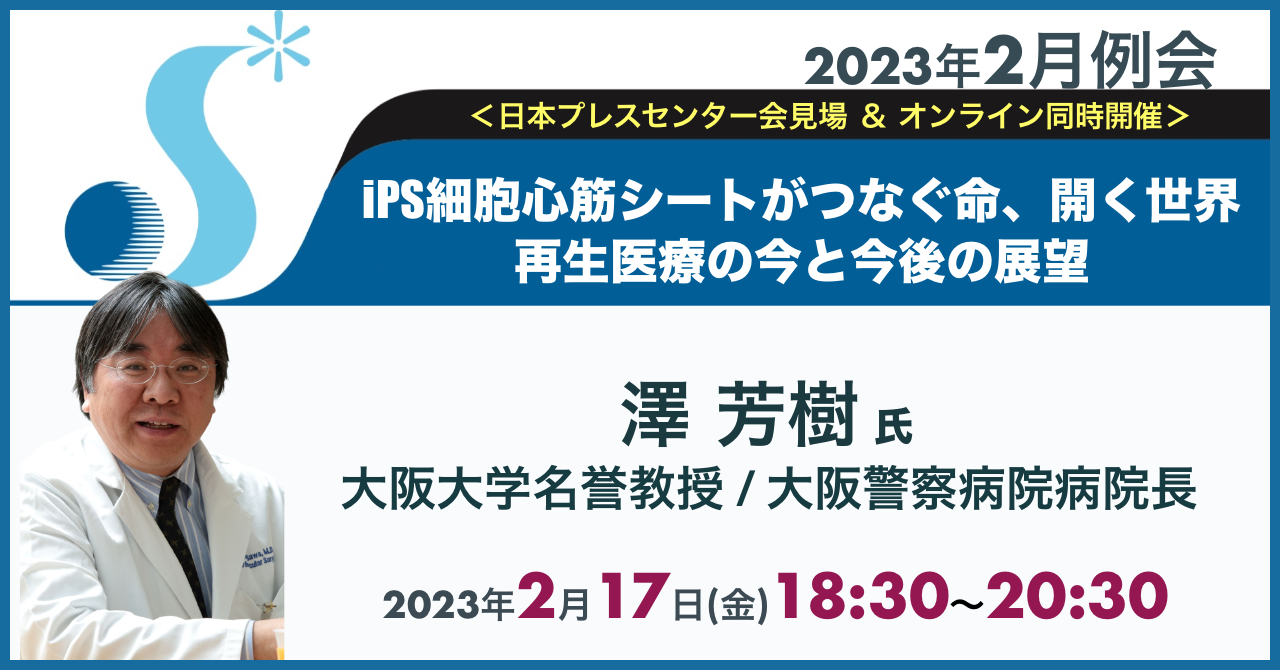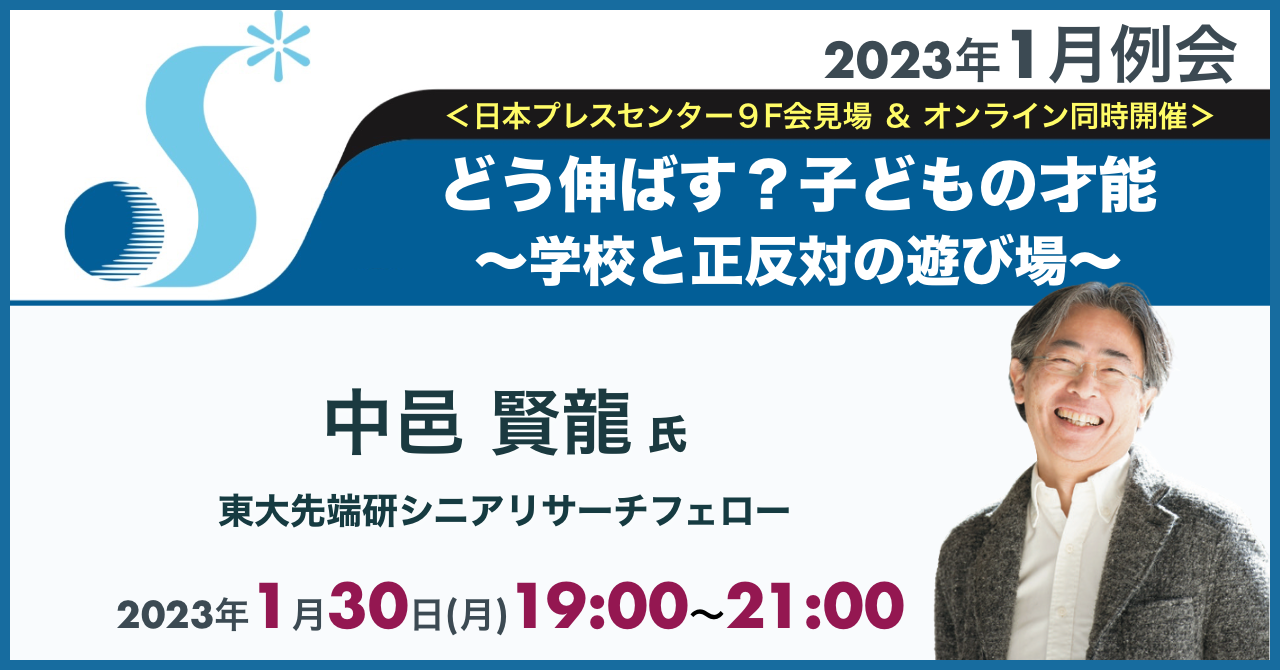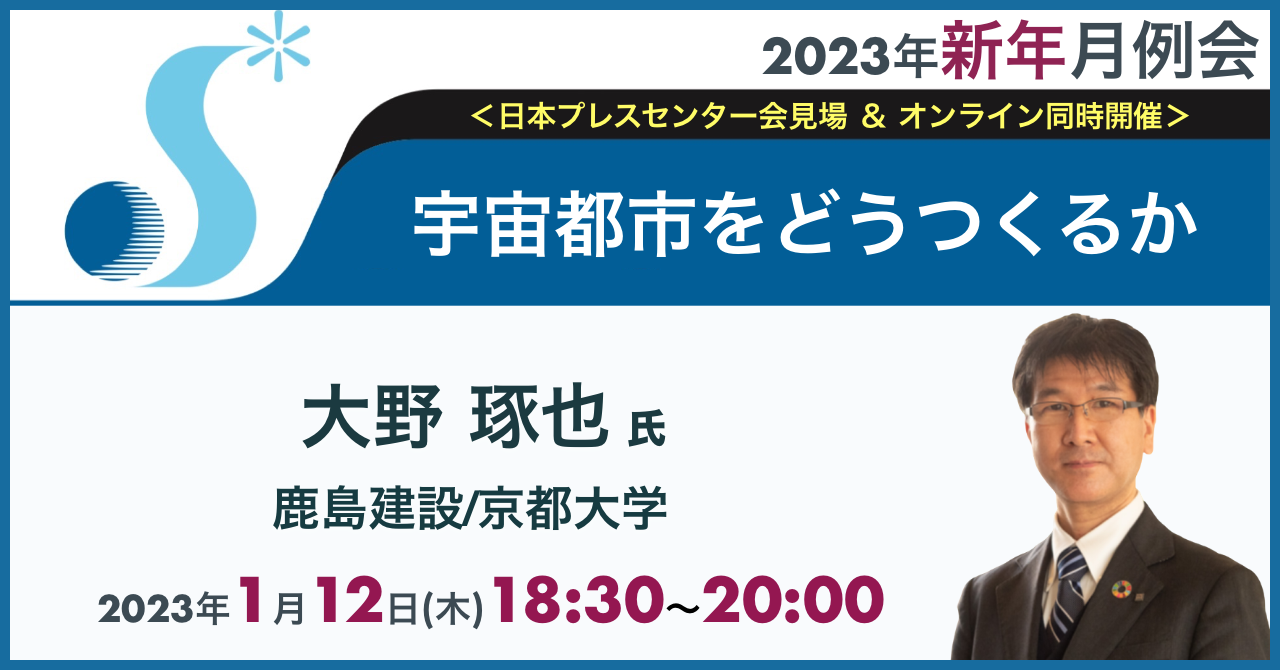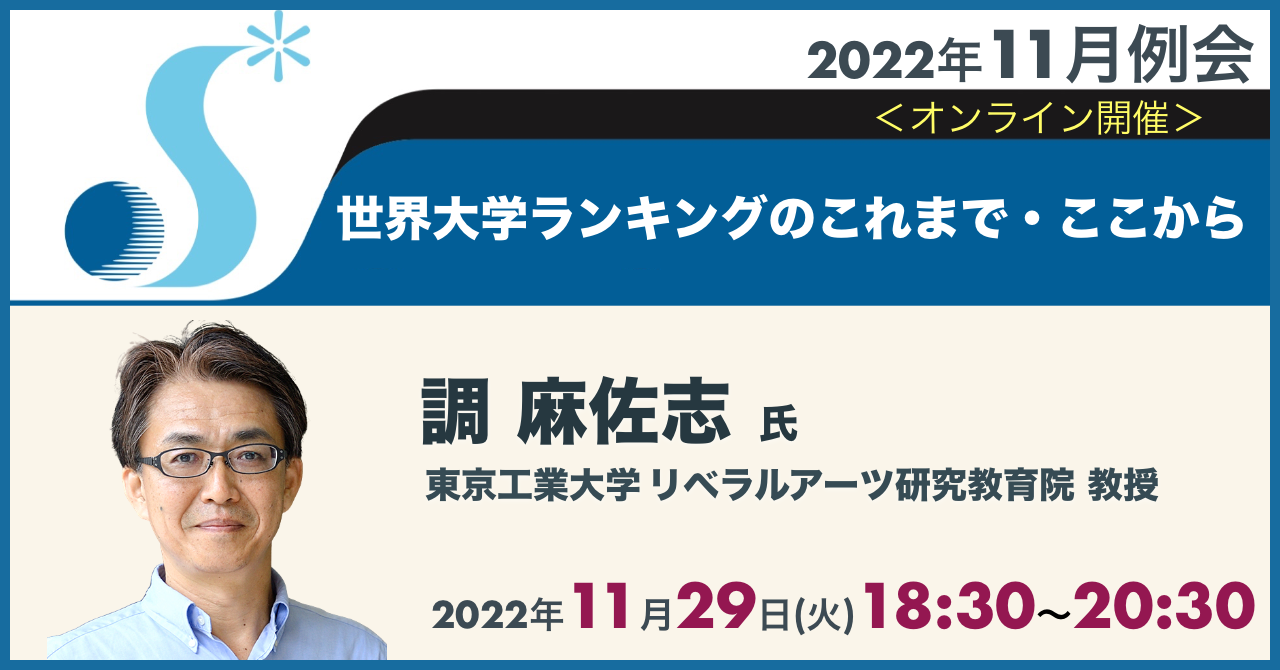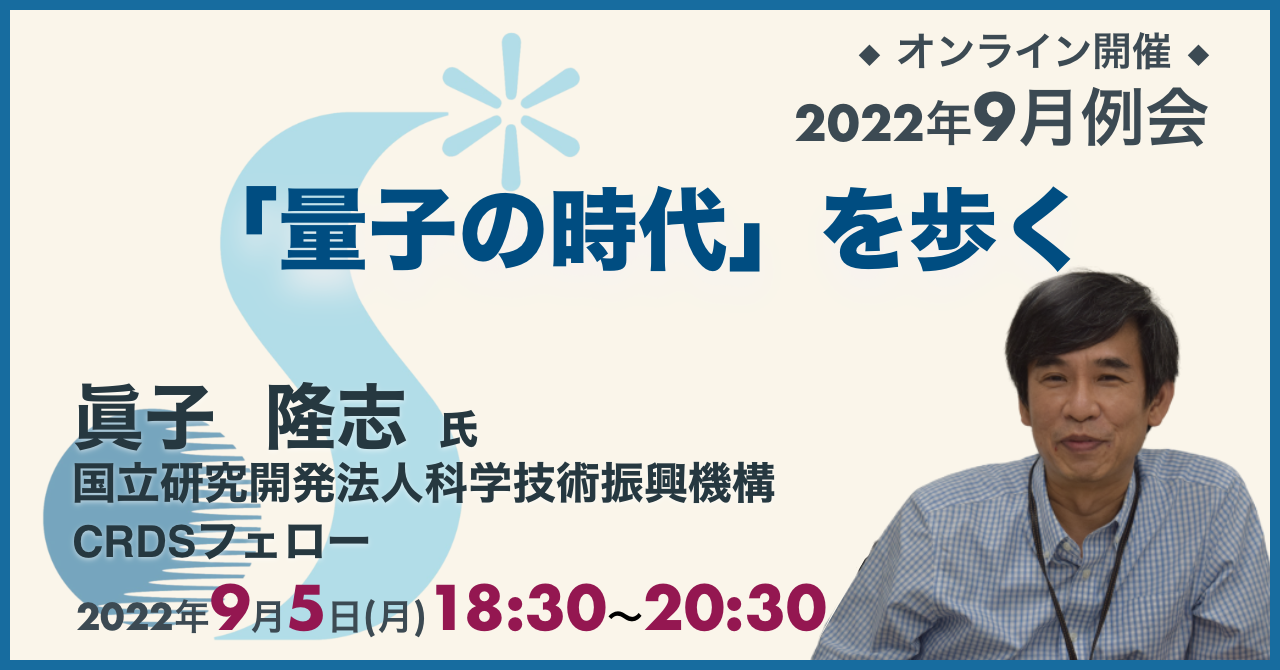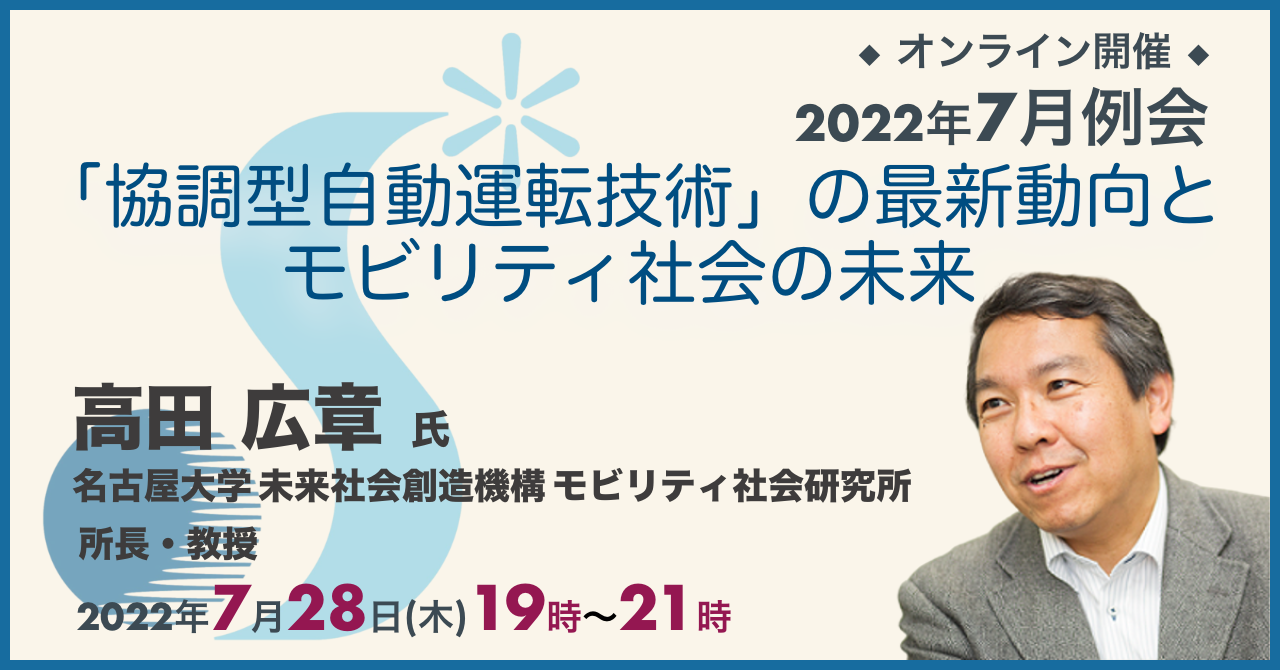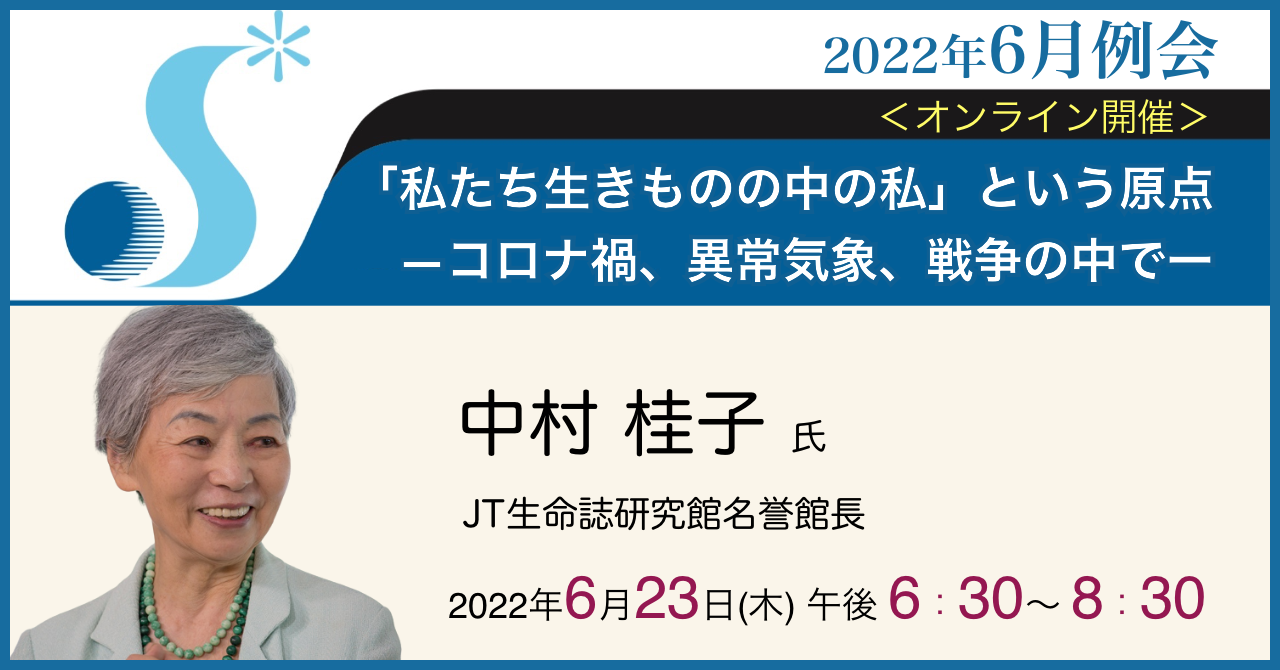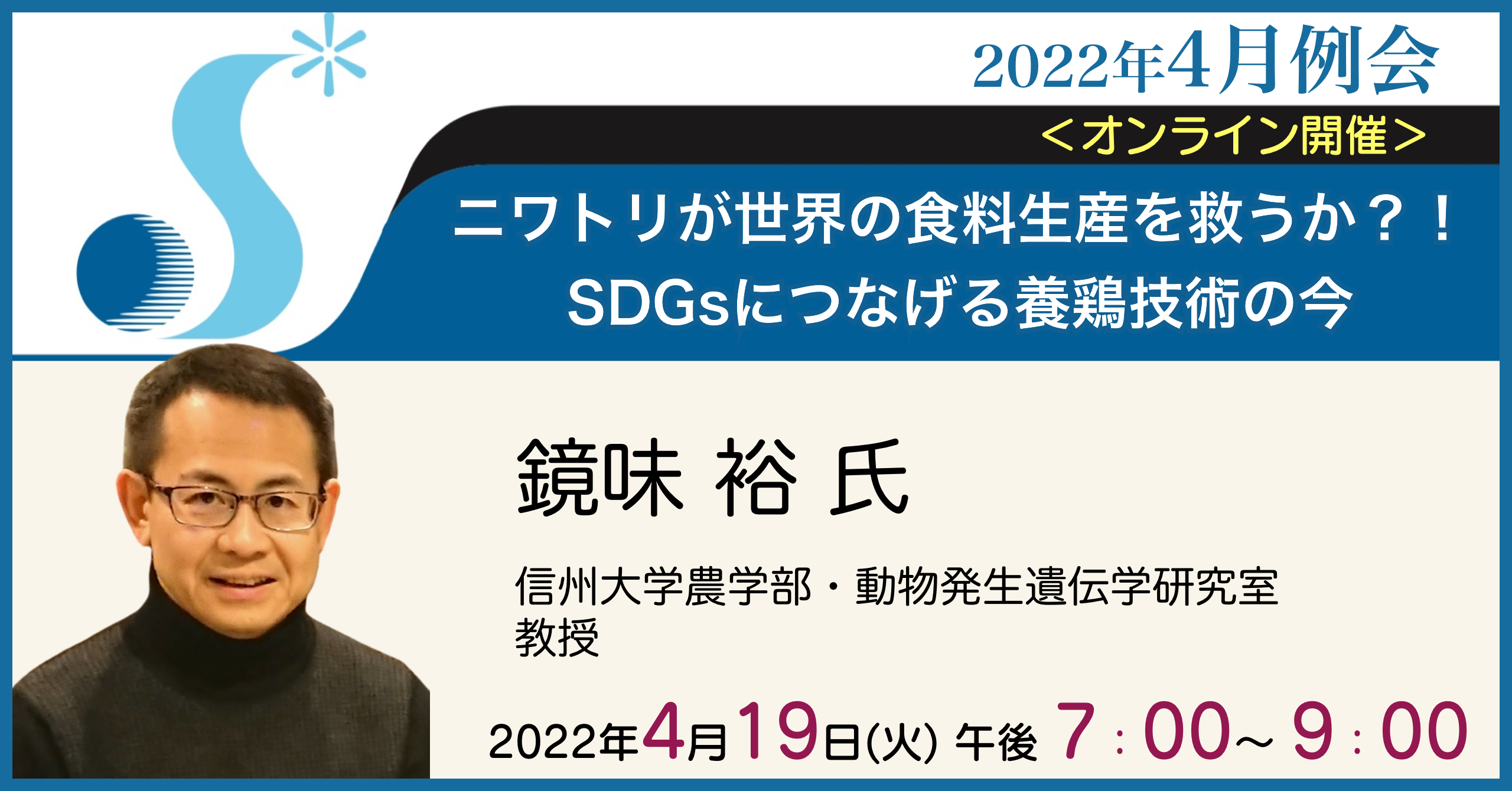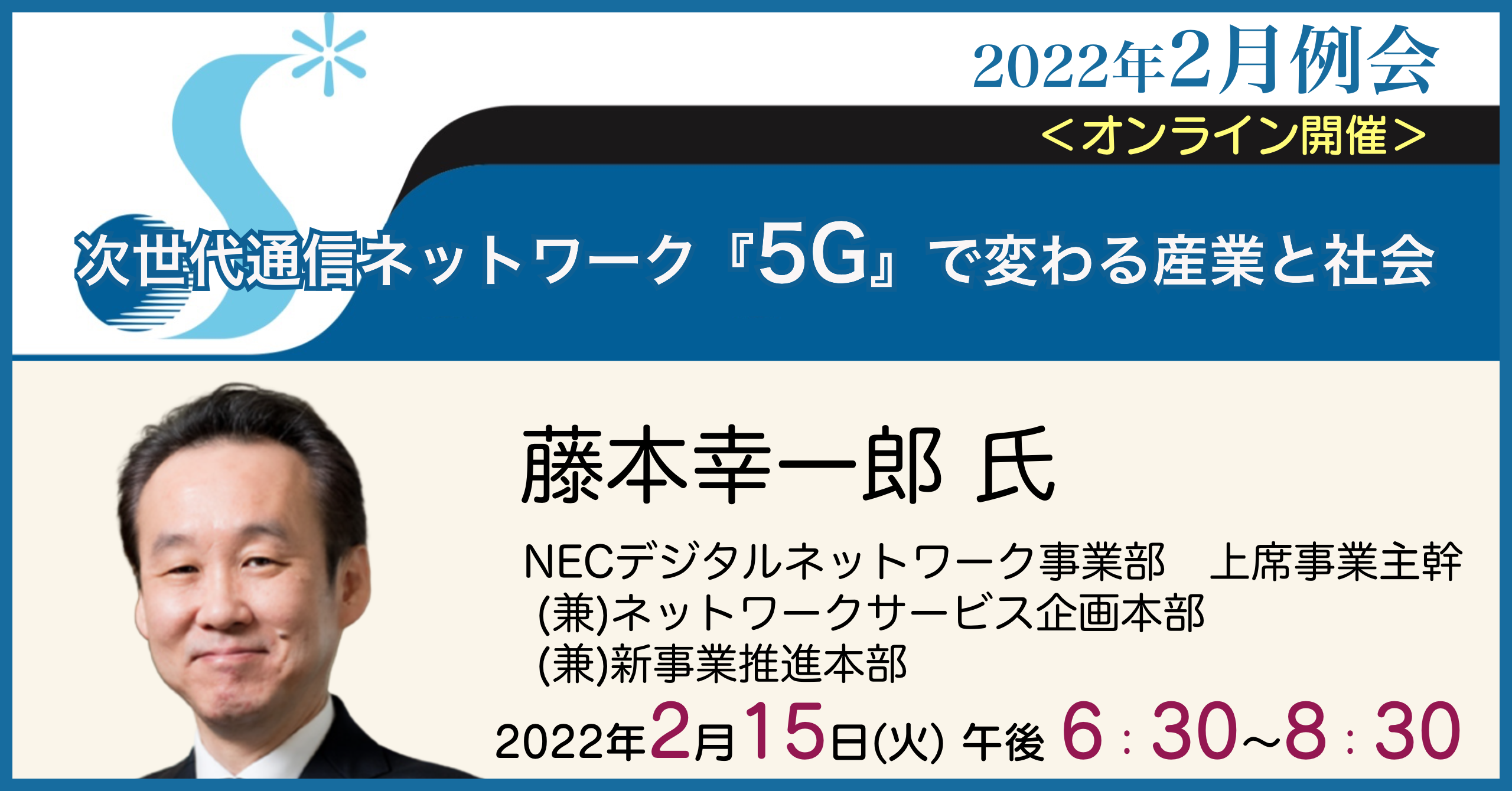「核」について学び直す
~核軍縮・廃絶の道はどこに~
講師: 秋山 信将(あきやま のぶまさ)一橋大学大学院法学研究科教授
日時: 2025 年7月10日(木) 午後6:30〜8:30
場所: 日本プレスセンタービル 9 階 小会議室(東京都千代田区内幸町 2-2-1)
ハイブリッド開催です。会員全員にzoom のURL を配布いたします。
ヒロシマ、ナガサキから 80年を迎える。しかし世界には核開発に邁進する国や、核を政治的・軍事的な恫喝にあからさまに利用する国がある。国際情勢の緊張の高まりを受けて、日本でも米国との「核共有」を提案する動きがある。2009年オバマ米大統領(当時)のプラハ演説で「核廃絶」への期待が高まったが、近年はそれに逆行する政治的・軍事的な動きが目立つ。
中国の核戦力台頭や小型戦術核の登場などで、冷戦期と異なり大国間の「核のバランス(核抑止)による平和」は成立しない恐れがある。核の惨禍から本質的に人類を守るには核廃絶と、それに至る「核軍縮」の追求が不可欠であり、核軍縮の取り組みが強く求められている。
世界の核保有状況はどうなっているのか。ロシアや北朝鮮の核の恫喝をどう捉えるべきなのか。核軍縮を進める上での障害は何か。「核共有」は核兵器を持たないとする日本の基本姿勢に抵触しないのか。専門家の話を聞き会員相互で意見交換したい。
秋山 信将さん略歴
1967 年生まれの国際政治学者(軍備管理、エネルギー安全保障などが専門)。一橋大学法学部卒、英オックスフォード大学で学び、広島市立大学広島平和研究所講師、日本国際問題研究所主任研究員などを経て、2012年に一橋大学教授。16年に大学を離れ、外務省在ウィーン国際機関日本政府代表部公使参事官を務める。18年から現職。この間、外務省核不拡散・核軍縮有識者懇談会委員や原子力規制委員会核セキュリティ検討会外部有識者、福島原発事故独立検証委員会(通称民間事故調)委員、NPT 運用検討会議日本政府代表団アドバイザー、外務省「核兵器のない世界」に向けた国際賢人会議委員などを務める。
JASTJ 担当理事 滝 順一
※会員の皆さまには開催の前日までにzoom のURL を送らせていただきます。
事前のお申し込みは不要です。なおURL は会員以外には転送しないようお願いいたします。
会場参加をご希望の方は当日、会場までおいでください。
※会員以外で参加希望の方は下記よりお申し込みください。申込締切7月3日(木)
申し込みURL https://conference-park.jp/reg/17
※会員と塾開催期間中の塾生は無料です。学生は500円、その他の方には参加費1,000円をいただきます。
★例会報告の原稿執筆者を募集
原稿は1,300字前後で締め切りは7月31日。ご協力いただいた方には図書券3,000円をお贈りいたします。原稿執筆に不慣れな方も歓迎いたしますので、執筆希望者は事務局までご連絡ください。
★月例会での取材活動について
月例会の内容を記事化する場合は、発言内容等に関し講師の方に改めて確認をとるようお願いします。質疑応答における質問者の方の発言についても同様です。
★JASTJ では政治的・社会的立場の如何にかかわらず、科学技術や科学政策、科学コミ ュニケーションの在り方などについて、深い視点から講演できる方をお招きしています。